最終更新日 2025年6月19日
古代ギリシャ哲学の言葉のひとつに「四元徳」という言葉があります。
現代でも「徳を積むといいことがある」と言われるように、「徳」という言葉には「良い行い」といったイメージを持っている人が多いでしょう。

では、より良い人生を生きるのに必要な「四元徳」とはいったいどういうものなのか。
この記事では、四元徳とはどういうものなのかについて解説していきます。
目次
四元徳とは
古代ギリシャの哲学者たちは、「人が悪い生き方をするのは、知識がないから」と考えていました。
人が良い生き方をするためには知識が必要であり、その知識というのが四元徳のことです。
四元徳とは「知恵・勇気・自制・公平さ」の4つの徳のこと。
四元徳(枢要徳)はソクラテスの弟子である、プラトンによる徳の説明に端を発します。
つまり、良い生き方というのは「知恵・勇気・自制・公平さ」が伴っている生き方ということです。
四元徳と知識は別物
四元徳は「知恵・勇気・自制・公平さ」の4つの徳のことですが、それぞれどういうものか簡単に解説すると以下のとおりです。
✅知恵は、複雑な状況に対処するための力。
✅勇気は、倫理的・道徳的に行動するための力。
✅自制は、欲望や欲求に振り回されずに忌避するための力。
✅公正さは、誰にでも平等に接するための力。
古代ギリシャにおいては、これら4つの徳に沿った生き方はすべて良い生き方であり、より良い人生を生きるために不可欠なものだと考えられていました。
そして、この4つの徳の力をうまく使いこなすためには、知恵とは別に「知識」が必要で、「知識こそ人間にとっての最高善である」とソクラテスは述べています。

つまり、知識を持った人間で「知恵・勇気・自制・公正さ」に沿った生き方が良い生き方であり、知識が欠如している人間の「知恵・勇気・自制・公正さ」がない生き方が悪い生き方ということになります。
良い生き方には四元徳がある
人間にとって正しいとされる良い生き方は、どんなものであっても知恵・勇気・自制・公正さを欠いていません。
どんな状況や環境に陥っても、目の前の現実を見据え、落ち着いて対処できる冷静な行動の中には「知恵」が。
倫理的・道徳的な行動には、その行動をするための「勇気」が。
暴飲暴食をせずに自分の欲求を抑える行動には「自制心」が。
そして、相手が子どもだろうと老人だろうと、あるいは自分にとって嫌いな人であろうと、誰にでも平等に接することができる人には「公正さ」という正義が備わっています。
良い生き方には、上述した4つの徳である四元徳が備わっているのです。
そしてそれは、知識があるからこそ発揮できる力であり、仮に徳が備わっていても、知識がなければ宝の持ち腐れで徳も錆びれてしまいます。
ここで述べている知識とは、勉強ができるかどうかの知識ではなく、自分に備わっているものを活用するための知識です。
時代が変わっても知識は重要
現代では私を含め、四元徳に沿った良い生き方を実践できている人は多くいません。
勇気と自制と公正さが人間にとって大事なものであることは理解できても、それらを実生活で実践することは簡単なことではありません。

特に社会的な豊かさは古代と現代とのもっとも大きな違いであり、もし仮にソクラテスが現代に来たとすれば、おそらくこう言うでしょう。
「君、君、私の奴隷はどこにいる?」
しかし、古代と現代で時代性そのものが違っているとしても、四元徳が現代において必要でなくなったわけではありません。
なんとなくでも、知恵・勇気・自制・公平さがある生き方と、四元徳がない生き方では、どちらのほうがより良い人生を生きられるかがわかります。
四元徳は、より良い人生を生きるための指針であり、なおかつ幸福な人生にも必要なものなのです。
四元徳を持って生きる方法
良い生き方・悪い生き方というのは主観的なものに見えますが、古代ギリシャの哲学者たちにとっては客観的なものでした。
世間に褒められるか非難されるかは関係なく、四元徳に沿った生き方こそ、人間によってただひとつの良い生き方だと考えられていたのです。

では、現代で四元徳を持って生きるにはどうすればいいのか。
自分にも他人にも良い影響がある行動をする
四元徳は良い生き方をするために必要なものです。
ですが、そもそも良い生き方と悪い生き方が、具体的にはどういった基準で判断されているのかは誰にもわかりません。
単純に考えば、法を犯し、警察に捕まるような行動は悪い生き方、他人に迷惑をかけたりするのは悪い生き方だと言えます。

自分の身を守ることは四元徳の「勇気」につながるもので、上述した状況では、母親を殺して自分を守る行動が四元徳に沿った生き方になるかもしれないのです。
もちろん、人を殺すのはどんな理由でも良い生き方とは言えませんが、状況によって良い生き方の意味が変わる場面では、自分にとっての徳のある行動を考えなければなりません。
自分が持っている知恵を最大限活用し、自分にとって徳のある生き方をする。
それは結果として周りの人たちを助けることにもつながります。
しかし、これは「自己中心的に生きろ」というわけではありません。
四元徳は自分にとっても、他人にとっても良い生き方であり、決して周りに迷惑をかける生き方ではないのです。
自分の人生も、そして他人の人生にも良い影響を与える行動が、四元徳に沿った生き方と言えます。
さまざまな分野の知識をつける
古代ギリシャ哲学の中では、悪い生き方というのは人間の無知によって引き起こされ、悪い生き方そのものを求めている人間は存在しないと考えられていました。
この考えの源は、すべての哲学の祖である、ソクラテスです。
人間が悪い生き方をするのは知恵が足りていないからであり、自分の頭で行動について考えられないからこそ、道徳的・倫理的に反した悪い生き方をしてしまう。
悪い生き方というのは人間の倫理や道徳に反した行動のことであり、古代では四元徳に反した知恵や勇気、自制や公平さを欠いた行動はすべて悪い生き方でした。
そうした悪い生き方をするとき、当の本人は自分が悪い生き方をしているとは思っていません。
辛辣ではありますが、無知なるがゆえに、悪い生き方を悪いと判断することができない状態なのです。

知識は読書や経験で身につけることができ、知識がついてくると内省によって何が悪い生き方なのかがわかってきます。
勉強ができるできないの知識ではなく、さまざまな分野の知識をつけることが、四元徳を持って生きるためにも必要なものです。
自分にできることから始める
ソクラテスからはじまり、ストア派の人たちも四元徳を重視し、徳のある生き方こそ幸福に生きる道だと考えていました。
四元徳は人格を鍛えるため、人間性を高めるために必要なものであり、四元徳に沿った生き方をすれば人生をより充実して生きられます。
四元徳を持って生きるためには、まず自分にできることから始めてみましょう。
たとえば、
✅知恵を身につけるために、たくさんの本を読む。
✅自分が正しいと思うことには、勇気を持って行動を起こす。
✅欲望に溺れないように、自制心を身につけて感情をコントロールする。
✅人によって態度を変えず、誰にでも公正に接する。
小さな行動でも、一歩踏み出して少しずつ日常生活の中での行動を変えていく。
日々の行動を変えることで、自然と四元徳に沿った生き方ができ、今よりも徳のある生き方ができるようになります。

完璧に四元徳に沿った生き方はできないかもしれませんが、一緒に少しずつ自分の生き方を変えていきましょう。
【オススメです】電子書籍「自分を知る15の質問」が今だけ無料で貰えます

自分のやりたいことや自分軸の見つけ方がわかります。
「DISCOVERYメソッド」で学ぶことで、自分のやりたいことや自分軸の正しい見つけ方がわかり、もう他人に振り回されることがなくなり、自分がすべきことを自分で決断できるようになるでしょう。
まとめ:四元徳は良い人生の指針
古代ギリシャの哲学者たちが重視していた四元徳は、古代でも現代でも良い人生を生きるために大事なものです。
人の脳は過去5万年前から進化していないと言われていますが、人間性や人格、美徳といった部分も過去二千年前とほとんど変わっていません。
知識はより良い人生を生きるために不可欠なものであり、悪い生き方を避け、良い生き方をしたいのであれば、四元徳を実践する必要があります。
悪い生き方を避ければ、無理に良い生き方をしようとしなくても、自然と人生は良くなっていく。
これは引き算的な考え方で、悪いものを排除していけば、残ったものはすべて良いものとなります。
より良い人生にしたい人は、自分の行動が四元徳に一致しているかどうかを指針としてみましょう。
自分の行動に自信が持てれば、たとえ結果がどうなろうと、自分は良い生き方をしたと胸を張ることができ、後悔のない人生が生きられるはずです。










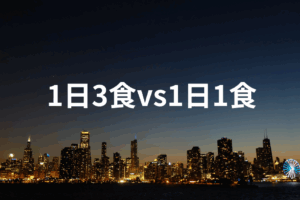



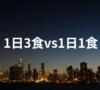
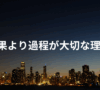
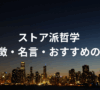
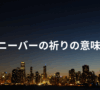
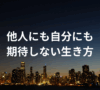

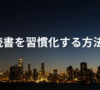
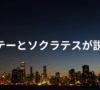
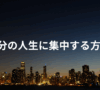

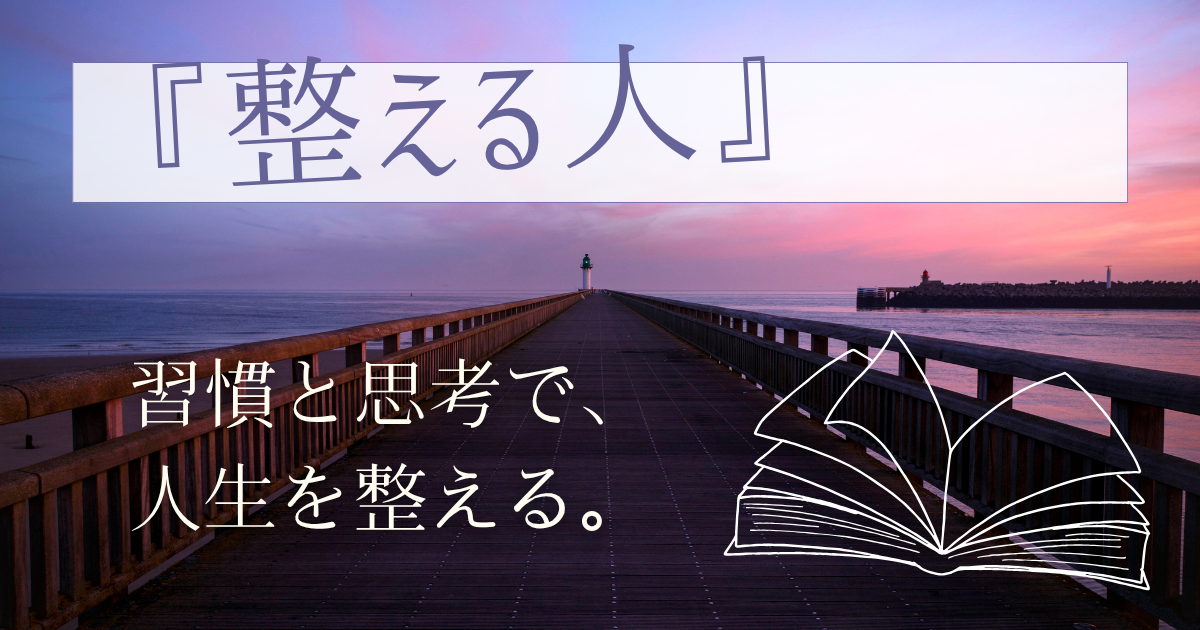
-300x158.jpg)

