最終更新日 2025年6月26日
- 「本当は〇〇が欲しいけど、手に入らないから別に要らない」
- 「頑張れば手に入りそうだけど、頑張るのがめんどうくさいし、実際そこまで欲しくない」
自分の本音は「欲しい」と言っているのにも関わらず、その本音を押し殺して自分に嘘をつく。
このような状態は心理学的に「認知的不協和」と呼ばれ、自分の中の矛盾を解消するために自分を欺く心理として解説されています。
認知的不協和になると、自分を無理やり正当化したり、自分に嘘をついて自己欺瞞の状態になるので注意が必要です。
この記事では、認知的不協和をわかりやすい具体例で解説していきます。
認知的不協和とは
基本的に、自分に嘘をつく人は認知的不協和になっている人が多いです。
認知的不協和は、心理学者であるレオン・フェスティンガーが提唱した概念で、以下のような状態のことを指します。
認知的不協和とは、人が自身の認知とは別の矛盾する認知を抱えた状態、またそのときに覚える不快感を表す社会心理学用語。
簡単に言うと、「本心と矛盾したことに対して不快感を感じる心理のこと」です。
イソップ童話の「酸っぱいブドウ」
認知的不協和をわかりやすく表している例は、イソップ童話の「酸っぱいブドウ」というお話です。
高い木の上にヨダレが落ちそうなほど美味しそうなブドウがあり、それを食べたくて見上げている1匹のキツネがいる。
しかし、キツネがいくら思い切りジャンプしたとしてもブドウまで届かず、いつまで経ってもブドウを手に入れることができない。
次第にキツネは「あんな場所にあるブドウは美味しいはずがないさ」と捨て台詞を吐き、自分が取れなかったブドウを蔑んでその場を立ち去っていく。
このキツネが陥っている状態が、認知的不協和状態です。
キツネは見つけたときはおいしそうに見えたブドウを、自分では手の届かない存在であると気づいたとき、そのブドウを「おいしくないブドウ」だと自分に言い聞かせています。
これは、「ブドウが欲しい」という気持ちと「ブドウが取れない」という気持ちを同時に抱えることで不快感を感じ、その不快感を解消するために自分に嘘をついている状態です。
人は認知的不協和になると不快感を感じ、その認知的不協和を解消しようとします。
「ブドウが欲しい⇒ブドウが取れない⇒不快感を感じる⇒あのブドウはきっとおいしくないと思い込む⇒不快感が解消される」
認知的不協和を解消するときに、人は自分に嘘をつくのです。
認知的不協和の解消は自分を守るため
認知的不協和の状態で不快感を感じると、ほとんどの人はその状態を解消しようとします。
それはつまり、認知的不協和の解消は自分を守るためにおこなわれるということです。
さきほどのイソップ童話のキツネの場合は、ブドウを自分の力では手に入れることができないため、ブドウに価値がないと自分に言い聞かせる(嘘をつく)ことで自分自身を守っています。
あなたも、以下のような経験をしたことはありませんか?
- 本当はお金が欲しいのに、人生はお金じゃないと言う。
- 異性からモテたいのに、恋愛に興味がないふりをする。
- やりたい仕事をしていないのに、自分は幸せだと言い聞かせる。
- 不満ばかりなのに、満足していると思い込む。
これらはすべて認知的不協和を解消するために、自分に嘘をついている状態です。
人が本音で生きられないのは、現実が本音とは矛盾する状態になっていて、認知的不協和を抱えているから。
その不快感を解消するために自分に嘘つき、本音を誤魔化し、自分を守るために本音とは違う考えを自分に言い聞かせるのです。
認知的不協和と自己正当化
認知的不協和と自己正当化には深い関係があります。
というのも、認知的不協和は自己正当化を引き起こし、間違った選択を正しいと思い込んでしまうのです。
たとえば、ダイエットをしているのに甘いものを食べてしまうときにも、認知的不協和と自己正当化が関係しています。
ダイエットしているから食べてはいけないとわかっていても、甘いものを目の前にすると、
- 「どうせ痩せない」
- 「これを食べるぐらい問題ない」
- 「たまには息抜きも必要」
といった、食べても大丈夫な理由をいくつも並べて自己正当化するのです。
「ダイエットして痩せたい」「甘いものが食べたい」という認知的不協和が、「ダイエットしてもどうせ痩せない」という認知的不協和の解消への行動を促します。
そして、認知的不協和を解消するために、自己正当化する。
「認知的不協和が起こる⇒認知的不協和を解消するために自己正当化する」
自己正当化についてもっと詳しく知りたい人は、以下の記事も読んでみてください。
認知的不協和と自己欺瞞
「自己欺瞞」というのは字のごとく「自分を欺くこと」で、言い換えると「自分に嘘をつく行為」のことです。
つまり、自己欺瞞と認知的不協和はほぼ同じ意味で、自分の中の不快感の感情を解消するために自分に嘘をつきます。
そして、自己欺瞞は自己正当化を引き起こし、無理やり自分のことを正しいと思い込むのです。
本心ではない行動を自分の本心であるかのように自分を欺き、自己正当化をする。
認知的不協和と自己正当化、自己欺瞞の3つはそれぞれ関連しあっていて、それぞれがそれぞれの原因であり結果です。
これらはすべて「自分を守るため」におこなわれ、言い換えれば自分を肯定するための手段でもあります。

ただし、自分に嘘をつくことで大きな選択を間違えることもあるので、不快感を解消するための行動には注意する必要があります。
認知的不協和のさまざまな例
ここからは、認知的不協和のさまざまな例を簡単に紹介していきます。
自分も経験がないかどうか、自分と照らし合わせながら読んでみてください。
仕事の認知的不協和の例|本当は転職したいのに…
毎日残業続きで疲れていて「本当は今の仕事を辞めたい」「もっとやりがいのある仕事がしたい」と思っているのに、「どこも同じ」「今の会社は安定してるし…」と自分に言い聞かせる。
これは「転職したいという本音」と「行動できない現実」との間に生まれる認知的不協和を、自分に嘘をつくことで解消している状態です。
恋愛の認知的不協和の例|本当は会いたいのに…
本当は好きな人に会いたいし、連絡をとりたいのに、「忙しそうだから」「こっちからばかり連絡するのは負けみたい」と理由をつけて距離をとる。
「会いたい」という本音と、「自分から連絡できない」という現実が矛盾していて、その不快感を自己正当化で和らげようとしています。
健康の認知的不協和の例|運動したくないから言い訳を…
健康のために運動しなければと思っていても、いざとなると「忙しいから無理」「自分は体質的に痩せにくい」と理由をつけて何もしない。
「運動したほうがいい」とわかっているのに行動できない自分を正当化しようとして、認知的不協和を無意識に解消しています。
人間関係の認知的不協和の例|本当は謝りたいのに…
友人や家族に対して本当は自分が悪いとわかっていて謝りたいのに、「あの人も悪い」「謝ったら負けだと思われる」と自分の非を認めないようにする。
「謝りたい気持ち」と「謝れない自分」の矛盾から生まれる不快感を、相手のせいにすることで正当化している例です。
認知的不協和への対処法
人は認知的不協和に直面すると、それを解消するために自分に嘘をつきます。
それが自己正当化や自己欺瞞につながり、自分の本音を誤魔化すことになるのです。
ここからは、認知的不協和に対処法を紹介していきます。
自分の素直な欲求を認める
認知的不協和に振り回されないようにするには、自分の中の素直な欲求を認めることが大切です。
本当はもっとたくさん稼いで色々なものが欲しいのにも関わらず、自分の力では今以上にお金を稼ぐことができない。
この矛盾を解消するため、「お金よりも大事なものがある」「モノをたくさん持っても意味がない」「仕事よりも自由な時間のほうが大事だ」と言う。
もちろん、本心からそうした生き方をしている人もいます。
ですが、多くの人は本心では納得していなく、認知的不協和から自分を守るために自分に嘘をつくのです。
心の中にある欲求を認めてしまうと、その欲求を満たせない自分に劣等感を感じてしまう。
だから人は、自己正当化や自己欺瞞をし、認知的不協和を解消しようとするのです。
自分の本音を誤魔化さず、自分に嘘をつくことなく、好きなものを好きと言い、欲しいものを欲しいと認め、欲求や欲望を否定するのではなく、人生を豊かにするものだと受け入れる。
自分の欲求を素直に認めることができれば、認知的不協和を解消するために自分に嘘をつくこともなくなります。
自分の価値観をハッキリさせる
人は無意識のうちに自己欺瞞と自己正当化している生き物です。
どんなに頭が良くて賢い人であっても、自分を正当化し、ときには自分に嘘をついて自分で自分を言い聞かせているもの。
認知的不協和に注意するときは、それが本当に自分の本音なのか、プライドや見栄から自分に嘘をついていないかを考える必要があります。
そのためには、自分の価値観をハッキリさせておきましょう。
- 自分は何を大切にして生きるのか。
- 何が自分にとって大切なのか。
- どういう生き方がしたいのか。
- 何をしているときが幸せなのか。
価値観を決めておくことで、認知的不協和になっても自分に嘘をつかずにすみます。
何を大事にするかをハッキリさせることは、自分の欲求を認めることと同じです。
自分に嘘をつく人の多くは、価値観がないために他人や周りの目に振り回され、自分を守るために嘘をつきます。
認知的不協和は、自分の価値観をハッキリさせておけば、ある程度対処できるものです。
「頭」ではなく「心」で考える
認知的不協和を感じたときは、「頭」ではなく「心」で考えるのが効果的です。
というのも、頭で考えてしまうと、本音との矛盾を解消するために自己正当化しがちになります。
一方、心で考えた場合は、欲求や欲望などの感情の動きがそのまま出るので、自己正当になりません。
✅頭で考える⇒あれこれ理由や言い訳を考え、認知的不協和の解消のために自己正当化しがち。
✅心で考える⇒感情の動きがそのまま出ているので、自分の本音が表れていることが多い。
感情は「自分がどう感じているか?」なので、感情の動きには嘘はありません。
欲しいものは欲しい、好きなものは好き、やりたいことはやりたいというように、認知的不協和になっても心は自分の本音を知っています。
自己正当化や自己欺瞞は、頭で考えるからこそ起こる状態です。
自分に嘘をつかないためには、行動するときは「頭」を使わずに「心」で感じたことを大事にしてみましょう。
【オススメです】電子書籍「自分を知る15の質問」が今だけ無料で貰えます

自分のやりたいことや自分軸の見つけ方がわかります。
「DISCOVERYメソッド」で学ぶことで、自分のやりたいことや自分軸の正しい見つけ方がわかり、もう他人に振り回されることがなくなり、自分がすべきことを自分で決断できるようになるでしょう。
まとめ
人が自分に嘘をつくのは、認知的不協和を解消するためです。
そして、認知的不協和を解消するために自己正当化をおこない、自己欺瞞で自分の本音と言動の矛盾を解消しようとします。
認知的不協和は誰しも起こりうる心理状態であり、プライドが高い人ほど自分の本心を欺きがちです。
認知的不協和に振り回されないように、自分の価値観をハッキリさせておきましょう。
自分の欲求を素直に受け入れられれば、本音を誤魔化すことなく自分らしく生きていけます。



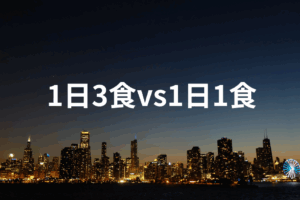



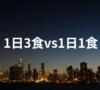
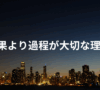
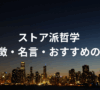
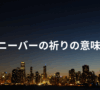
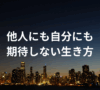

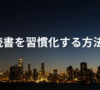
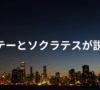
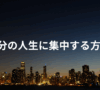

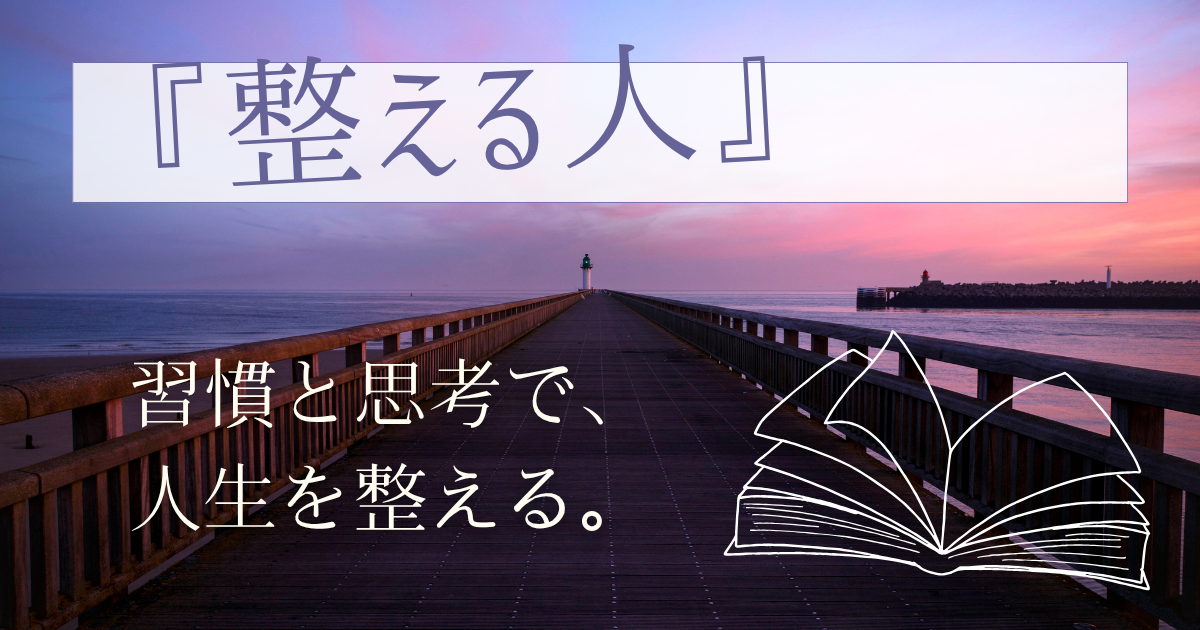
-300x158.jpg)

