最終更新日 2025年6月19日
古代ギリシャにはソクラテスをはじめ、プラントやアリストテレスといった現代にも語り継がれる聡明な哲学者が数多く存在していました。
彼らの知恵は数千年後の現代にも役に立つものが多く、ソクラテスの「無知の知」といった格言をはじめ、先人たちの哲学は現代社会を生きる人にとっても重要なものです。
そうした中で、昔から語り継がれている格言の一つに「汝自身を知れ」というものがあります。
この言葉は、アポロン神殿のデルフォイの神託というものであり、古代ではデルフォイの神託を神の予言として人々の運命を左右するものとされていました。
この記事では、デルフォイの神託について詳しく解説していきます。
目次
デルフォイの神託とは?
デルフォイの神託は、古代ギリシャにおいて宗教的・文化的な中心地として機能した、アポロン神に捧げられた神聖な場所です。
デルフォイは、紀元前8世紀頃から神託の中心地として栄え、アポロン神の神託を伝える巫女(ピュティア)によって運営されていました。
ピュティアはトランス状態に入り、神の言葉を口に、これを神官が解釈し、相談者に伝えるのがデルフォイの神託というものです。
このプロセスは神秘的で、古代の人々にとって神の意志を知る重要な手段でした。
デルフォイの神託は、単なる予言ではなく、倫理的・哲学的な指針を提供することも多く、相談者の決断を導く役割だったのです。
この点が、後のソクラテスの哲学に影響を与えた要因の一つでもあります。
デルフォイの神託の格言「汝自身を知れ」の意味
「汝自身を知れ」という格言は、アポロン神殿に刻まれた「デルフォイの神託」というものです。
デルフォイとは、ギリシャの中部にある古代都市デルフォイの「聖域」として知られる場所であり、デルフォイにあるアポロン神殿の入り口に「汝自身を知れ」「Meden agan」という2つの格言が刻まれています。
プラトンの「プロタゴラス」の中では、ソクラテスが「七賢人が神殿に集まりこの碑文を残した」と書かれていますが、実際には誰が書き残したのかはハッキリしていないようです。
では、「汝自身を知れ」「Meden agan」という2つの言葉には、いったいどういう意味が込められているのか。
汝自身を知れ
「汝自身を知れ」という言葉は、おそらく誰もが一度は聞いたことがある格言です。
この言葉は、人生の道に迷っているときや、やりたいことがわからないとき、生きる意味や人生の選択に悩んでいるときなどによく使われ、一般的には、「汝自身を知れ=自分自身を知れ」という意味として解釈されています。
自分自身を知るというのは、自分はどういう人間なのか、何が好きなのか、何を求めているのか、何がしたいのか、どこに行きたいのかといった、いわば自己分析をして自分自身を理解するという意味です。
ですが、ここで疑問が思い浮かびます。
「汝自身を知れ」という言葉を残した人は、本当にそうした意図を持ってこの言葉を残したのか。

というのも、「汝自身」とは「私」ではく、すなわち「人間」のことなのではないでしょうか。
人間という生き物を理解せよ
汝自身を知れというのは「人間を知れ」という意味であり、「自分は何が好きなのか」といった自己分析をしろという意味ではありません。
「人間という生き物を理解せよ」という、神の存在が絶対的に信じられていた時代ゆえの言葉であると思うのです。
現代では個人主義が広く行き渡り、若者をはじめ多くの人が「個」に集中しています。
これからは個の時代だと言わんばかりに、自己分析やら自分探しの方法などがSNSやネットに溢れているのが現状です。

そして、デルフォイの神託のもう1つ「Meden agan」という言葉にも、「汝自身」が「人間」を指していることを裏づける意味が込められています。
Meden agan(度を越すなかれ)
アポロン神殿に刻まれた格言として「汝自身を知れ」を知っている人は多いです。
ですが、もう一つの格言である「Meden agan」について知っている人はあまり多くありません。
Meden aganは古代ラテン語で「度を越すなかれ」という意味であり、「過剰の中の無」という意味で解釈されることもあります。

というのも、「度を越すなかれ」という言葉も「何事もほどほどが一番」という意味の言葉ではなく、「人間の限界を知れ」という意味の言葉だと解釈できます。
人間の限界を知れ
ギリシャ神話にはゼウスをはじめ、オリュンポス十二神として多くの神々が登場しているとおり、古代ギリシャ時代では神が本当に実在していると疑っていませんでした。
神は運命を絶対的なものとして掲げ、人間と自然を創造し、この世界と宇宙をもコントロールしていると思われていたのです。
神の存在は絶対的なものであり、何者にも邪魔することはできず、神に逆らうことなどもってのほか。
神が創造した人間が神に近づこうなどとは考えてはいけないこと、人間が神になろうとするのは神への冒涜、侮辱である。
そうした考えが古代ギリシャではあたり前であり、疑いようもない真実だったのです。
だからこそ、多くの人々への警告として、先人たちはアポロン神殿のデルフォイの神託に「Meden agan」、「度を越すなかれ」という言葉を刻んだのではないでしょうか。
デルフォイの神託とソクラテス
デルフォイの神託は古代ギリシャと深いつながりがありますが、実はソクラテスとも関係があります。
ソクラテスとデルフォイの神託の関係は、彼の哲学の出発点として決定的な役割を果たしたのです。
プラトンの『ソクラテスの弁明』に描かれるエピソードを中心に、その詳細を見ていきます。
「ソクラテスはもっとも賢い」という神託
ソクラテスの友人カイレフォンは、デルフォイの神託に「ソクラテスより賢い者はいないか」と尋ねました。
神託の答えは明確でした。
「誰もソクラテスより賢くない。」
ソクラテスは自分は賢くないと自覚していたため、デルフォイの神託に困惑します。
彼はむしろ、自分が無知であることを自覚していたのです。
そして、ソクラテスは「神託が真実なら、その意味を探らなければならない」と考え、「本当に賢い者は誰か」を探す哲学的な探究が始まりました。

そこで、ソクラテスはデルフォイの神託の真意を理解したのです。
「無知の知」の誕生
ソクラテスは、神託の言葉を次のように解釈しました。
「自分は何も知らないと知っている。だからこそ神は自分を“最も賢い”といったのだ」
つまり、
✅他人:無知なのに知っているつもり(=無知の無知)
✅ソクラテス:自分の無知を自覚している(=無知の知)
この「無知の知」は、ソクラテス哲学の核心を成す概念です。
彼は、知識を自慢する人々に対して、質問を通じて彼らの無知を暴露しました。
この手法は「ソクラテス式問答法」として知られています。
- 質問の提示:相手に特定の概念(例:正義、勇気)について定義を求める。
- 反論と掘り下げ:相手の答えに矛盾や曖昧さがある場合、さらなる質問で深掘りする。
- 無知の認識:最終的に、相手が自分の知識の限界に気づくよう導く。
この問答法は、批判的思考を養うための方法であり、現代でもよく使われているテクニックです。
ソクラテスの裁判
デルフォイの神託は、ソクラテスの人生の後半、「不敬罪」と「若者を腐敗させた罪」の裁判にも影響を与えました。
ソクラテスは、裁判で神託のエピソードを語り、彼は、神託に従い、真理を探求する使命を果たしてきたと主張。
しかし、アテナイ市民の多くは、彼の問答法を傲慢と受け取ったのです。

神託の言葉が、彼の行動の正当性を裏付ける一方で、社会的軋轢を生んだのです。
裁判の結果、ソクラテスは死刑宣告されました。
彼は、毒杯を飲むことで命を終えましたが、脱獄をそそのかされても、最後まで自分の信念を貫きました。
そして、ソクラテスの死は、後の哲学者たちに大きな影響を与え、プラトンやアリストテレスは、ソクラテスの思想を引き継ぎ、哲学をさらに発展させたのです。
【オススメです】電子書籍「自分を知る15の質問」が今だけ無料で貰えます

自分のやりたいことや自分軸の見つけ方がわかります。
「DISCOVERYメソッド」で学ぶことで、自分のやりたいことや自分軸の正しい見つけ方がわかり、もう他人に振り回されることがなくなり、自分がすべきことを自分で決断できるようになるでしょう。
まとめ:デルフォイの神託は死と向き合うための格言
デルフォイの神託には、人間として生きる上で大切な格言が刻まれています。
それが「汝自身を知れ」と「Meden agan」という言葉です。
この2つの格言は、私たちが人間であるということを思い出させ、いつか死すべき存在であることを教えてくれます。
ソクラテスは自己探求のための言葉として「汝自身を知れ」を解釈しましたが、別の角度からの解釈を考えるのも大事なことです。
デルフォイの神託に刻まれた格言は、現代人に対して死と向き合う大切さを教えてくれる言葉です。
個人主義が強く根差している現代だからこそ、私たちは自分が「個」である前に、一人の「人間」であることを意識するのが大事なのだと思います。
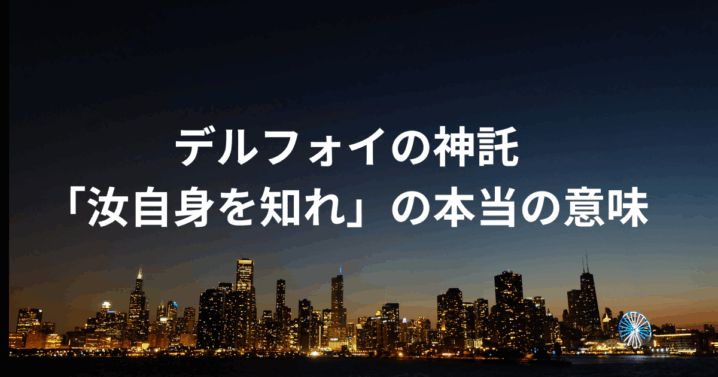



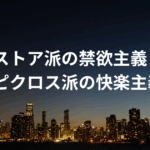







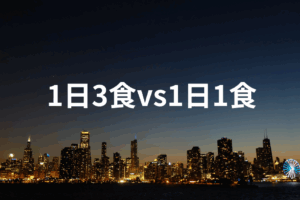



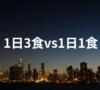
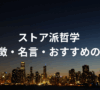
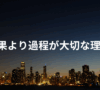
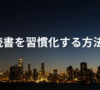
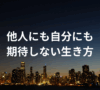


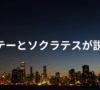
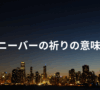
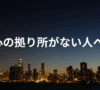
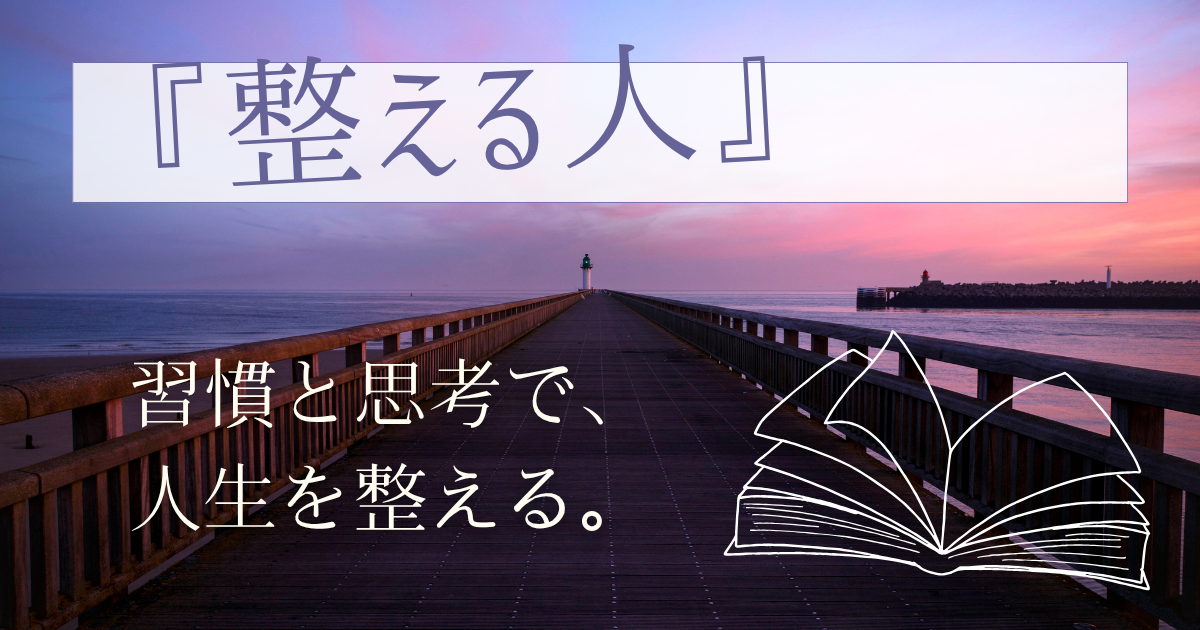
-300x158.jpg)

