最終更新日 2025年6月19日
世の中では、自立は「自分でお金を稼ぎ、親元を離れて一人暮らしをし、自分の力で生活している状態」だと思われています。
- 社会人になって一人暮らしをすれば自立。
- 就職して自分をお金を稼げるようになれば自立。
- 親元から離れて自分の生活をすべて自分でやるようになれば自立。
しかし、それは本当に「自立した状態」と言えるのか。
はたして親元を離れて一人暮らしをしているだけで自立したことになるのか。
どんな人でも、実家暮らしをしている人は自立しているとは言えないのか。
今回の記事では、一人暮らしだけが自立ではない理由、本当の意味で自立するために必要なことを解説していきます。

本当の自立とはどういう状態なのか興味がある人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
一人暮らし=自立は間違い
近年は「自立できていない大人が増えている」とよく耳にします。
いい歳して実家暮らしをし、結婚もせずに親に甘えた状態で暮らしている人のことを、世間では「自立できていない大人」とレッテルを貼る。

そこでまずは、現代の自立の意味について見ていき、一人暮らしだけが自立ではない理由を解説していきます。
一人暮らしの思い込み
そもそもの問題として、
- 「社会人=自立しなければならない」という風潮はいつから生まれたのか?
- 「一人暮らし=自立」という認識は、いつから世間の当たり前になったのか?
- 大人になったら、必ずしも一人暮らしをしなければならないのか?
こういうことを思ったりしたことはないでしょうか。
よく、大学生がお金がなくて困っている様子をSNSなどで見かけたり、社会人になっても給料が低く、満足した生活を送れないと嘆いている人もいます。
ですが、なぜ経済的な悩みを抱えているのにも関わらず、実家を飛び出し一人暮らしをしているのか?
なぜお金がないとわかっていながら、お金がかかる生活をわざわざ自分で選んでしまうのか?

「社会人になったら親元を離れ、自分の力で生活するのが普通」という世間の常識を自分で勝手に背負い込み、自分で自分を追い詰めているのです。
本来なら自分の生活は自分で決めるべきであるにも関わらず、世間の目や常識を気にして「一人暮らししないと」と思い込んでしまっています。
自立にはお金がかかる
「一人暮らし=自立」と思っている人は、「社会人になったら、一人暮らししなければならない」と思い込んでいます。
一人暮らしをしていれば、一人前の大人としてしっかり生きているような気がするし、頑張って自立している自分を誇らしく思う人もいるかもしれません。
ですが、現実的には多くの人たちがお金の問題で生きづらさを感じています。
「自立しなければならない(一人暮らししないといけない)」と思い込むことで、つらくても自分でお金を稼ぎ、自分の力で生活しなければならないと思い込む。
「生きてるのが楽しくない」「お金がなくてつらい」と言っている人の多くは、自分で自分を追い込んでいることに気づいていません。
一般的な意味でいう「自立」にはお金がかかります。
何度も言うように、世間では「自立=一人暮らし=自分でお金を稼いで生活すること」と思われているため、お金と自立は切り離せない関係です。
そのため、多くの人は世間的な目や周りからの目を気にして、無理してでも自立しようとします。

にも関わらず、多くの若者や大人たちが、お金に困っていながら一人暮らしに執着するのはなぜか?
それは「自立」が現代のイデオロギーとして、世間一般に深く根づいているからにほかなりません。
現代の「自立」は経済的な自立
就職して自分でお金を稼ぎ、親元を離れて一人暮らしをし、自分のことは自分でやる。
それが「人として自立する」と思っている人が大多数です。
たしかに、自分で自分が生活するためのお金を稼ぐことは大切なこと。

ですが、自分が生活するためのお金を稼ぐというのは、「経済的な自立」という自立の言葉に含まれた一つの意味でしかありません。
そして、経済的に自立人しているからといって、人として自立していることの証明にはならないのです。
「自分でお金を稼いでいれば自立している」「一人暮らししていれば自立している」と考えるのは、経済的な側面からしか自立を考えていません。
しかし、それだと「お金がない大人は自立できない」と勘違いをしてしまいます。
いい歳して実家暮らししている人のことを、「子ども部屋おじさん(おばさん)」と揶揄したりしますが、これは不動産屋が儲けるためにつくられた言葉です。
自立はお金のあるなし、経済的な側面だけで測れるものではありません。
自立で大事なのは精神的な自立
一人暮らしだけが自立ではないとすれば、自立するには何が必要なのか。
それは、精神的な自立です。
いくら経済的に自立していたとしても、精神的に自立していなければ一人前の大人とは言えません。
もちろん、精神的に自立していたとしても、経済的に自立できていないのであれば、本当の意味で自立しているとは言えないでしょう。
精神的な自立とは、人間関係の自立のことであり、他人に依存したり執着せず、自分一人だけでも人生を楽しく生きられる精神のこと。
とはいえ、精神的な自立をするために人間関係を捨てる必要はありません。
家族や友達、恋人や同僚と楽しい時間を過ごすことも、人生の醍醐味であり幸せの形の一つです。
精神的な自立で大事なのは、他人に対して過度に依存や執着、期待をしてはならない、ということ。
✅他人に依存しない
✅自分で決断し、自分の選択に責任を持てる
✅一人の時間も充実して過ごせる
✅自分の感情を自分でコントロールする
自立とは精神的に成熟した状態
精神的に自立できていない人は孤独耐性が低く、ちょっとでも寂しさを感じると、友達と遊ぶ約束をしたり、恋人に電話をかけたりします。
一人でいる時間の孤独感に耐えられず、常に誰かとつながりを求めてしまう。
もちろん、それが悪いことではありませんが、「他人がいないと楽しくない状態」になってしまうと、精神的にいつまでも子どものままです。
精神的に自立できていないと、他人に依存して執着することでしか楽しさや充実を感じることができなくなってしまいます。
自立は「どこで暮らしているか」ではなく、「どう生きているか」で決まります。
本当に自立した状態とは、内面、つまり精神面が成熟した状態のことなのです。
本当の自立に必要な3つの条件
現代で「自立」と言えば「一人暮らししているかどうか」で判断されますが、本当の意味での自立とは「他人に依存していない状態」です。
では、本当の意味で自立するために必要なことはなにか。
ポイントは、以下の3つ。
- 経済的な自立は最低限必要
- 人間関係からの自立
- 他人に依存しない
経済的な自立は最低限必要
「自立=一人暮らし」ではないにしろ、自立するためには最低限自分の生活は自分の稼ぎでする必要があります。
社会人になっても親からお小遣いをもらっている状態は、一人暮らしだろうが実家暮らしだろうが自立しているとは言えません。

もちろん、1人ひとり事情があるのは言うまでもないことですが、「自立」という観点から見れば、「仕送りは自立できていない状態」となります。
経済的自立のポイントは「経済的に自立しているかどうか」であり、自分の生活を自分の稼ぎで成り立たせている状態。
実家暮らしや一人暮らしというのは、経済的自立には何の関係もありまません。
経済的な自立はあくまでも、「自分1人のお金で生活できるかどうか」が判断基準となります。
ですが、たとえ実家暮らしでも、生活費を渡し、自分のことを自分でやっているのであれば、経済的な自立は達成できます。
自立とは「他人に依存していない状態」のことですが、それは実家暮らしでもできるのです。
人間関係からの自立
自立においては、精神的な自立が何よりも大事です。
精神的な自立を考える上で大事なのは、以下のようなポイント。
✅自分1人でも人生を楽しめる
✅他人に依存や執着をしない
✅自分で考え、自分の意思で行動できる
この中で特に重要なのが、他人から自立しているかどうか。
実際、経済的に自立している人の中にも、他人から自立している人は少なかったりします。
たとえば、お金はあっても寂しくて毎日遊びまわり、常に誰かとつながっていないと落ち着かない人は、精神的に自立できていません。
人間関係で大事なのは、数ではなくお互いの関係性です。
精神的な自立をするには、他人に依存することなく、一人で生きていける心の強さを持つことが不可欠。
この観点から言えば、経済的に自立をしていても、実家暮らしをしている人の中には精神的に自立できていない人もいます。
「寂しいから実家暮らしのほうがいい」「常に家に誰かいてほしい」という人は、精神的に自立できていない状態です。

大切なのは、「他人がいなくても人生を楽しめるかどうか」です。
他人に依存しない
現代では推し活が精神の安定になっている人も多いですが、自立という観点から考えるとあまり良くない状態です。
もちろん、推しがいることで仕事を頑張れたり、嫌なことにも耐えられたり、楽しみがあって幸せに生きられるという人もいます。
ですが、他人に自分の人生の舵を握られているような状態、つまり、推し活が依存になっている場合には注意が必要です。
依存とはそれなしでは生きられない状態であり、自分で自分の機嫌を取れなかったり、人生の舵を他人に任せている状態のこと。
好きな人がいるのは素晴らしいことですが、それが依存になってしまうと、好きな人の言動に一喜一憂することになります。
推し活には「私を楽しませてくれる」という期待が込められており、他人に期待するのは「裏切り」などの感情を生むことにもつながる。
期待については、以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある人は読んでみてください。
推しや好きな人がどんなことをしようがその人の自由、しかし、何か気に入らないことがあれば勝手に失望し、勝手にショックを受ける。
これは精神的な自立ができていない典型的な症状であり、まさしく他人に依存している状態です。

人生の舵はしっかり自分自身で握り、他人に依存するのではなく、他人と自分との距離を適切に保てる人が、本当の意味で自立している人間なのです。
【オススメです】電子書籍「自分を知る15の質問」が今だけ無料で貰えます

自分のやりたいことや自分軸の見つけ方がわかります。
「DISCOVERYメソッド」で学ぶことで、自分のやりたいことや自分軸の正しい見つけ方がわかり、もう他人に振り回されることがなくなり、自分がすべきことを自分で決断できるようになるでしょう。
【まとめ】自立は経済的自立と精神的自立の2つが合わさったもの
一人暮らしをしている人を見ると、世間からすれば「自立している人」のように見えます。
ですが、自立は一人暮らしをした状態ではなく、自分の生活を自分で稼いだお金で成り立たせ、他人に依存していない状態のことです。

自立は一人暮らしで得られるものではなく、お金を稼いでるから自立しているわけでもありません。
世間体や他人の目を気にすると、「自立するには一人暮らししないといけない」と思い込んでしまいますが、それは間違いです。
お金も大切ですが、本当に大切なのは精神的な成熟、他人に依存しない心なのです。




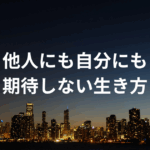

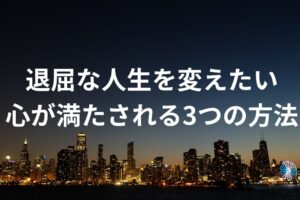



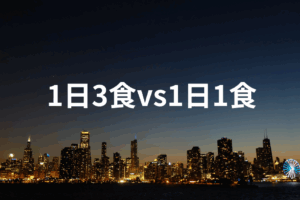



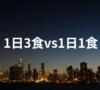
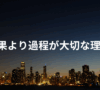
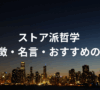
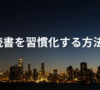
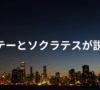
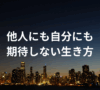
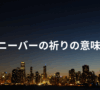


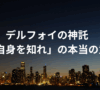
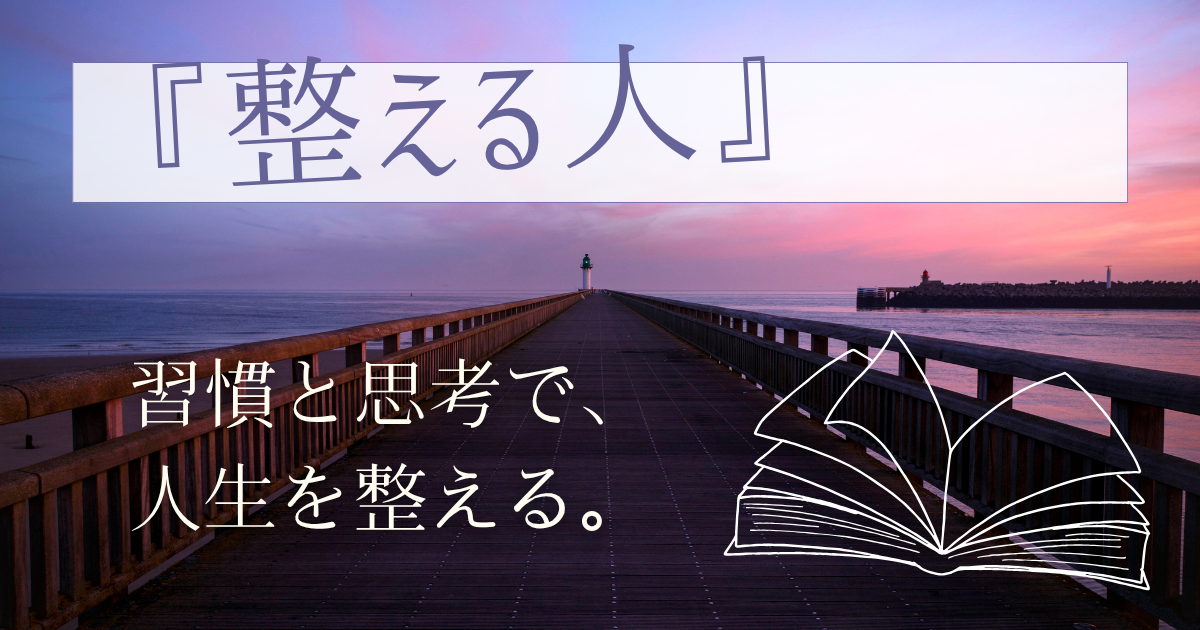
-300x158.jpg)


この記事を最後まで読ませていただきました。自分は発達障害と軽度精神障害を抱えている35歳の男で実家に暮らしていますが最近親から『出ていけ』を言われているわけでもないのに勝手に妄想して親に対して『出て行ってほしいんだろ』を言ってしまって親から『なんでそんなことを言うのか』と言われてしまい自分自分を追い込んでしまっています。でもこの記事を読んで『自立=一人暮らし』ではないんだということが少し分かったような気がします。ですので来年から精神的に自立できるように頑張ろうと思いました。