最終更新日 2025年6月22日
近年、世界中でストア派の哲学が注目されています。
ストア派は約2000年前の古代ギリシャの哲学であり、ゼノンという人が創始した哲学です。
一見、「2000年前の哲学が現代に何の役に立つのか?」と思うかもしれませんが、人間の悩みというのは昔も今もほとんど変わっていません。
だからこそ、より本質的な悩みについて実践的な知恵を説いていた、ストア派の哲学が現代でも役に立つのです。

この記事では、ストア派とはどういった哲学なのかを解説し、後半ではストア派の哲学を学ぶのにおすすめの本を紹介していきます。
ストア派とはどういう哲学なのか、学ぶのにおすすめの本が知りたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
ストア派とは
まずストア派とはどういう哲学なのか、具体的にはどういう思想を持った人たちなのかを簡単に解説していきます。
ストア派の核となっている思想は、以下の3つです。
- 心穏やかにより良く生きること。
- 自然に従って生きること。
- アパテイアで自分の運命を受け入れること。
心穏やかにより良く生きること
ストア派とは、キティオンのゼノンが紀元前3世紀に創始した哲学派のことです。
今ではヘレニズム時代を代表する哲学として親しまれ、古代ギリシャ時代では「ストア派」「アカデメイア派」「エピクロス派」「ペリパトス派」は四大学派と呼ばれるほどの力を持っていました。
ストア派の哲学は人によって解釈が異なりますが、
「自らの運命を受け入れ、感情を手懐ける方法を知り、アパテイアを身につけ、心穏やかにより良く生きること」
がストア派の本質となっています。
つまり、「人間が自由で幸福に生きるためにはどうすればいいか?」を、追求していくのがストア派の目的です。
ストア派とエピクロス派の違い
ちなみに、ストア派と似ている思想に「エピクロス派」という学派があり、ストア派とエピクロス派はよく「禁欲主義」と「快楽主義」として対比されています。
ストア派は運命を受け入れ、精神的な鍛錬によって「不動心(アパテイア)」を手にすることが目的の哲学です。
それに対しエピクロス派は、愛情や友情、その他人間に含まれる自然的で必要な欲求を追求する「快楽主義」という立場になります。
こちらは「心の平穏(アタラクシア)」を目指すのを目的とし、できるだけ世間から隠れて生きることで、心の平穏を達成しようとする哲学です。
✅ストア派⇒禁欲主義。欲に振り回されるのではなく、欲を手懐ける生き方。不動心(アパテイア)が目的。
✅エピクロス派⇒快楽主義。自然な欲求を追求し、隠れながら平穏に暮らす生き方。心の平穏(アタラクシア)が目的。
一見、両者は対立する思想のように感じますが、ストア派もエピクロス派も、自由と幸福について追求し、人間として幸せに生きることを目指している点で共通しています。
ストア派の禁欲主義と、エピクロス派の快楽主義の違いについて、もっと詳しく知りたい人は以下の記事も読んでみてください。
自然に従って生きる
次に、ストア派の重要な思想の一つ、「自然に従って生きる」ことについてです。
人生は、生きていれば自分ではどうすることもできない出来事がたくさん起こります。
その一つひとつの出来事に反応し、恨んだり憎んだり怒ったり悲しんだりしていれば、生きることに疲れてしまいます。
ストア派は、外的な出来事に振り回されないために自らの運命を受け入れ、感情を手懐ける必要があると考えました。
「自然に従う」とは、私たちの力が及ばないもの(天気、他人の言動、社会の評価など)を無理に変えようとせず、それらに感情を乱されることなく、今ここで自分にできる最善を尽くすという生き方です。
ストア派の代表的な実践者であり、古代ローマ帝国の哲学者だったセネカは、毎日すべてを失う覚悟をして生きていたと言われています。
実際、セネカは皇帝ネロに自害を命じられ、取り乱すことなく命を絶ちました。

しかし、それは物事を諦めるという意味ではありません。
諦めることと受け入れることは別で、前者は受動的な生き方ですが、後者は能動的な生き方です。
ストア派の人たちは能動的に人生を生き、自由と心の平穏を大切にしていました。
アパテイアで自分の運命を受け入れる
ストア派は自分の運命を受け入れることを重視しています。
それは、人は自分にとって嫌な出来事や悲しい出来事が起きると、本能的にその出来事を恨んだり憎んだりしてしまうからです。
ですが、何かの出来事が起きたときにその出来事から教訓を学び、自分の運命だと受け入れる考えを持つことで心の平穏を実現できます。
そして、自分の運命を受け入れるためには自分の感情をコントロールし、アパテイアを手に入れなければなりません。
アパテイアとは、感情そのものを否定することではなく、「怒りや恐れに飲み込まれずに、冷静に対応する能力」を意味します。
感情を持たないのではなく、感情に支配されないことが大切なのです。
たとえ明日仕事をクビになろうが、恋人に振られようが取り乱さない。
ガンが見つかり闘病生活になろうが、感情を取り乱すことなく、自分の運命を受け入れて生きる。
ストア派が大事にしていたのは何よりも心の平穏であり、心の平穏を実現するためにアパテイアを目標としていたのです。
ストア派を学ぶのにおすすめの本
ここまで、ストア派とはどういう哲学なのかについて解説してきました。
そしてここからは、さらにストア派について学びたい人におすすめの本を紹介していきます。
おすすめは、以下の10冊です。
- 迷いを断つためのストア哲学
- 良き人生について
- ストア派の哲人たち
- 奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業
- 人生談義
- 生の短さについて
- 自省録
- ストア派哲学入門
- 認知行動療法の哲学
- 心穏やかに生きる哲学
それぞれ簡単に内容を紹介していきます。
迷いを断つためのストア哲学/マッシモ・ピリウーチ
ストア派についての本をはじめて読むのであれば、マッシモ・ピリウーチの「迷いを断つためのストア哲学」が断然おすすめです。
この本はストア派の思想の隅から隅まで解説されており、実生活の中でどのようにストア派の哲学を生かせばいいのかについても詳しく述べてあります。
前半はストア派の基本的な思想を解説し、後半では「普段どのようなことを意識すればいいのか」といった実践的な知恵も学べます。
ストア派に関心がある人すべてに自信を持っておすすめできる本です。
✅人生の選択に迷い、不安を抱えている人
良き人生について/ウィリアム・B・アーヴァイン
アーヴァインの「良き人生について」では、ストア派のはじまりから実践の仕方、人生や心理面でのアドバイスが的確に述べられています。
ストア派を知るだけでなく、「より良い人生を送るためにはどうすばいいのか」といった深い部分まで知ることができ、実生活の中で本当に役立つ知恵が学べる本です。
人生や生き方、幸福から人間関係まで、人生における悩みのすべてをカバーしている良書だと言えます。
✅幸福や善き生き方の本質を哲学的に考えたい人
ストア派の哲人たち/國方栄二
「ストア派の哲人たち」では、ストア派の前身であるキュニコス学派から初期のストア派まで詳しくまとめられています。
もちろん、セネカやエピクテトス、マルクス・アウレリウスなどのストア派を代表する人物の思想も詳しく紹介されているので、これ一冊でストア派の知恵をインプット可能です。
ストア派の思想の痒い所にも手が届く内容となっているため、本格的にストア派を学ぶのであればぜひ読んでおきたい一冊。
✅ストア派の歴史や主要人物の思想を一気に知りたい人
奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業/荻野 弘之
「奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業」では、ストア派の実践者であるエピクテトスの知恵をマンガで読めるようになっています。
実際の生活の中で抱える悩みや問題、人間関係や感情のコントロールなどについて、その場でエピクテトスからアドバイスをもらえるように学べる本です。
人生の悩みは大抵「仕事」「お金」「人間関係」に集約されますが、それぞれについて「どう向き合えばいいか」を教えてくれます。
人生に悩みを抱えている人は、一度読めば今までとは違った視点で人生を生きられるようになるはずです。
✅逆境にいる今こそ、心の自由を手に入れたい人
人生談義/エピクテトス
エピクテトスの「人生談義」は、人生で必ず直面する苦難や悲しみに対する心の持ち方を学べる名著です。
人生の幸福は外部の出来事ではなく、自身の判断や態度に依存するとし、誰でもいますぐに幸せになれると説きます。
コントロール可能なのは自分の意志や感情のみであり、外部の事象(他人の行動や結果)は受け入れるべきであるというのが、エピクテトスの核心です。
簡潔で実践的なアドバイスは、現代でも自己啓発やストレス対処の指針としてもおすすめの一冊。
✅古典の深い人生観を、対話形式で気軽に味わいたい人
生の短さについて/セネカ
古代ローマにおいて、ストア派の実践者として有名なのがセネカです。
この記事でも述べてきたとおり、セネカは死ぬまでストア派として生きた唯一の実践者でもあります。
特に「生の短さについて」では、ストア派がどう生きるべきかについて詳しく述べられているので、かなり刺激的です。
ストア派のみならず、人生の生き方について教えてくれる良書なので、哲学に興味がある人はぜひ読んでみてください。
✅時間の大切さを見つめ直し、今を本気で生きたい人
自省録/マルクス・アウレリウス
マルクス・アウレリウスの「自省録」は、おそらくストア派に関する本でもっとも有名な本の一つです。
自省録には第16代ローマ皇帝であったアウレリウスが、自分に言い聞かせる日記のような形で、ストア派の哲学を日々実践していた記録を読むことができます。
内容的にも読みやすく、誰でも簡単に実践できる内容なので、日々の生活で参考になることが多いです。
こちらもセネカ同様、ストア派を理解するのに必須の本。
✅心を整え、静かに自分と向き合いたい人
ストア派哲学入門/ライアン・ホリデイ
時間にあまり余裕がない人は「ストア派哲学入門」を毎日1ページずつ読むことで、手軽にストア派の思想を知ることができます。
タイトル通り、ストア派の入門書といったところです。
セネカをはじめ、マルクス・アウレリウスやエピクテトスといった、ストア派の偉人たちの言葉が網羅されていて、はじめての人でもとても読みやすくなっています。
哲学の本は難しいものが多いですが、この本は1日1ぺージ読むだけで基本的なストア派の思想をインプットできます。
✅ストア哲学を基礎から体系的に学びたい初心者
認知行動療法の哲学/ドナルド・ロバートソン
ドナルド・ロバートソンの「認知行動療法の哲学」は、認知行動療法(CBT)とストア派哲学の深い関係を探る本です。
CBTは、古代ストア派の理性による感情の制御という思想に起源を持つ療法で、ストア派の知恵が現代でも役に立っていることがわかります。
心の平穏を得るため、思考の歪みを修正し、外部の出来事への反応を理性で管理する方法など、ストア派の知恵が満載。
実践的なワークブックとしても機能し、読者が自己の感情を理性で整える「心の筋トレ」を通じ、現代のストレスや不安に対処する方法が学べる本です。
✅心の癖や思考パターンを変えたい現代人
心穏やかに生きる哲学/ブリジッド・ディレイニー
「心穏やかに生きる哲学」では、ストア派の哲学を現代のストレス社会に適用する方法が学べます。
セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスらの教えを基に、コントロール可能な自身の思考や態度に焦点を当て、不安やFOMO(取り残される恐怖)を軽減する手法を紹介。
仕事やSNSの圧力、人生の不条理に対処し、時間を意識的に使う重要性について述べられています。
著者の経験を交えた情緒的な語り口で、ストア派の知恵を日常に活かし、心の平穏を得る具体的な方法がわかる本です。
✅ストレスに流されず、落ち着いた日常を送りたい人
【まとめ】ストア派の哲学は現代を生きる知恵
ストア派は古代の哲学でありながら、現代の私たちが直面する悩みやストレスに対しても有効な処方箋を与えてくれます。
✅感情に振り回されない生き方
✅運命を受け入れ、今を生きる力
✅他人や環境に左右されず、自己を整える力
このようなストア哲学の教えは、きっとあなたの人生にも役立つはずです。
まずは気になる一冊から手に取って、ストア派の知恵に触れてみてください。













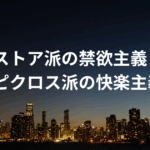


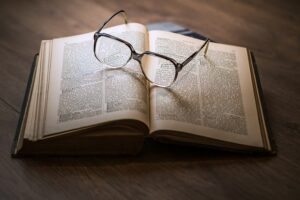

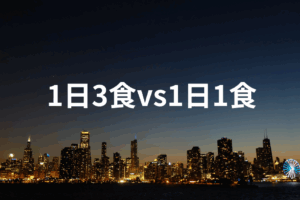



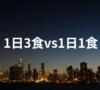
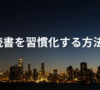
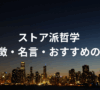
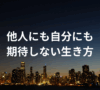

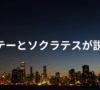
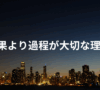

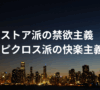
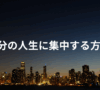
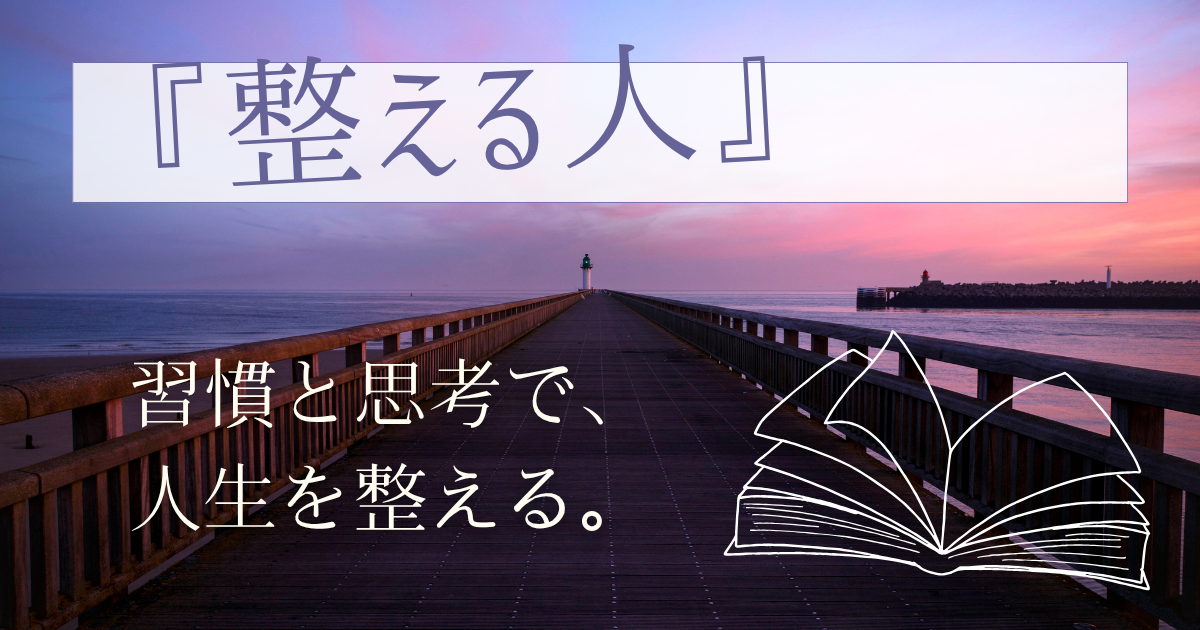
-300x158.jpg)

