最終更新日 2025年6月25日
近年、脳科学についての研究が日進月歩で進んでいます。
昔と比べてはるかに脳について深くわかるようになり、それに伴い人間の心理についての理解も深まりました。
しかし、現在でも脳のはたらきのすべてを解明できていなく、どちらかというとわかっていないことのほうが多くなっています。

ですが、脳について今わかっていることだけでも学べば、今までとは違う世界が見えてくるものです。
そこで今回の記事では、私が実際に読んだ、脳科学を学ぶのにおすすめの本を厳選して紹介していきます。
脳科学に興味がある人は、ぜひ参考にしてみてください。
脳科学を学ぶメリット
脳科学についての本を紹介する前に、脳科学を学ぶメリットを解説していきます。
私が思う脳科学を学ぶメリットは、以下の4つです。
- 人間がどういう生き物なのかがわかる。
- 自己認識を深められる。
- 脳のバイアスに騙されなくなる。
- 決断と選択の後悔を減らせる。
人間がどういう生き物なのかがわかる
脳科学というのは、その名のとおり、脳の機能について研究する学問のことです。
脳は外からの情報を処理する場所であり、視覚や認知、記憶や学習、予測や思考、言語や問題解決、意思決定から感覚の入力などを司っています。
昔は脳にはそれぞれの感覚や機能に対応する「モジュール」が存在するという説が一般的でした。

脳科学は脳の機能や認知といった部分に焦点を当て、状況や環境に対して脳がどういう状態になるのかを探っている学問です。
ほかにも、脳科学に関する本の中では、「脳がいかに「私」という人間を作っているのか」という問題を取り上げているものも多いです。
つまり、脳科学を学ぶことは「人間という生き物を知る」という意味でもあります。
自己認識を深められる
さきほどは、脳科学を学ぶことは「人間という生き物を知る」という意味だと言いました。
それをさらにかみ砕いて言うと、「脳を知る」というのは「自分を知る」ということでもあります。
脳は毎日休みなく意識を生み出す仕事をしており、人が眠りにつくと意識を失い、目を覚ますと意識が覚醒するように、人間に「自己」という概念を与えているのが「脳」という偉大な物体です。

たとえば、事故などで脳の一部に大きな怪我を負うと、以前とは性格が180℃変わってしまう人もいるのです。
特に大脳辺縁系などに障害があると、恐怖などの情緒的な反応がなくなることも実験からも明らかになっています。
脳がどのように「私」という人格を生み出しているのかはわかりませんが、脳を知ることで自己認識を深めることができるのです。
脳のバイアスに騙されなくなる
脳科学を学ぶメリットの3つ目は、脳のバイアスに騙されなくなることです。
これは心理学にも通じる話ですが、人間の脳には「バイアス」というものが存在します。
バイアスとは簡単に言うと先入観や思い込みのことですが、バイアスに騙されると間違った選択をしてしまいます。
バイアスは現実の認識を歪め、都合のいいように物事の解釈を変えてしまうのです。
- 人生での選択や決断を間違ってしまう。
- 思い込みで判断して、失敗や後悔をしてしまう。
- 自己正当化の罠に引っかかってしまう。
自分の行動が正しいと思っていたとしても、それは脳が自分を自己正当化しているだけかもしれません。
自己正当化は主観的なものであり、客観的なものではありません。
そして、主観的な判断は、大きな間違いへとつながることが多いです。

そうした脳のバイアスから身を守ってくれるのが、脳科学なのです。
脳科学を学ぶのにおすすめの本10選
ここからは、私が実際に読んだ、脳科学を学ぶのにおすすめの本を厳選して紹介していきます。
今回の記事で紹介する脳科学のおすすめ本は、以下の10冊です。
本屋に行けば、脳科学について書かれている本はたくさんありますが、専門的な本だとはじめての人はまったくわかりません。
そのため、以下で紹介する本は比較的読みやすく、はじめて脳科学に触れる人にもわかりやすい本を取り上げています。
脳科学は人格を変えられるか?/エレーヌ・フォックス
脳科学を学ぶのにおすすめの1冊目は、エレーヌ・フォックスの「脳科学は人格を変えられるか?」です。
この本は脳を「悲観脳」と「楽観脳」に分け、脳の状態によって物事の意味づけが変わることについて書かれています。
著者は楽観脳を「サニーブレイン」、悲観脳を「レイニーブレイン」と名づけ、脳の状態は後天的に変えられることを明らかにしました。
ほかにも、扁桃体や側坐核、セロトニンといった脳の理解に不可欠なことにも触れているため、脳科学に馴染みのない人にも読みやすいです。
まさに脳科学の入門書といっても過言ではないおすすめの1冊。
✅ポジティブ思考や性格を科学的に変えたい人
脳はいかに意識をつくるのか/ゲオルク・ノルトフ
2冊目は、ゲオルク・ノルトフの「脳はいかに意識をつくるのか 」です。
この本は主に意識について詳しく書かれている本であり、脳の異常から心の謎を解き明かしています。
人は何を知り、何を知らないのか、人間の意識とはどのようなものなのか、そして脳は自己をどのように認識しているかなど、脳について深く踏み込んでいる本です。
また、脳が生み出す心の問題として抑うつや統合失調症といった症状についても詳しく述べられていて、心脳問題に興味がある人も楽しめます。
脳や心、意識についてなど、幅広く知りたい人はぜひ読んでみてください。
✅意識のメカニズムに深く興味がある理系脳の人
〈わたし〉はどこにあるのか/マイケル・S・ガザニガ
3冊目は、マイケル・ガザニガの「〈わたし〉はどこにあるのか」です。
この本は認知神経科学の世界的権威、ガザニガの脳科学講義になります。
内容としては脳の機能やモジュールについて取り上げ、脳と「わたし」との関係について述べている本です。
人間のありようから、脳の騙されやすさやバイアス、無意識に影響される脳の解釈や自由意志といった概念にまで踏み込んでいます。
脳科学に興味がある人にとっては知的好奇心を刺激する1冊です。
✅哲学と脳科学の接点を考えたい人
人間らしさとはなにか?/マイケル・S・ガザニガ
4冊目は、ガザニガの代表作でもある「人間らしさとはなにか?」です。
この本は「人間とはなにか」を理解するための最高の科学書であり、脳科学の到達点と言っても過言ではありません。
「人間らしさとはなにか?」「脳のどこがユニークなのか?」最先端脳科学の答えが詳細にまとめられており、人間に秘められた謎が明かされています。
600ページを超える大書となっていますが、その分得られる知識や学ぶべき点が多いです。
読み終えると、今までと違う視点で自分と他人を見ることができます。
✅人間の本質や自由意志を科学的に探りたい人
意識は傍観者である/デイヴィッド・イーグルマン
5冊目は、デイヴィッド・イーグルマンの「意識は傍観者である」です。
この本も脳と意識の関係性について深く踏み込んだ本であり、知られざる脳の機能について深く教えてくれます。
脳が犯す過ちから、五感を脳がどう解釈するのか、脳と心の問題や、脳に振り回されずに生きる方法など、実践的な内容も描かれているのでわかりやすいです。
知識のない人にもわかりやすくまとめられているので、はじめて脳科学に触れる人でも読みやすくて理解しやすくなっています。
読みやすく、おもしろい脳科学の本を探してる人におすすめの1冊です。
✅無意識の力に支配される「自分」を知りたい人
あなたの脳のはなし/デイヴィッド・イーグルマン
6冊目「あなたの脳のはなし」は、「意識は傍観者である」と同じ著者である、デイヴィッド・イーグルマンの本です。
内容な前著に似ていますが、人間の脳がいかにして「現実」を作り出し、私たちの行動や感情をコントロールしているのかを平易な言葉で解説しています。
自由意志、無意識、記憶の曖昧さなど、私たちが当たり前と思っている感覚がいかに不確かであるかを明らかにし、「自分とは何か?」という問いを脳科学の観点から問い直している本です。
1冊目がおもしろいと感じた人におすすめ。
✅脳の仕組みをやさしく楽しく学びたい初心者
意識はいつ生まれるのか/ジュリオ・トノーニ
7冊目は、天才脳科学者と呼ばれるジュリオ・トニーノの「意識はいつ生まれるのか」です。
この本は、意識に関して唯一、真に有望な基礎理論とも言われる本であり、脳科学の最先端理論について述べられています。
脳科学では「意識」が一番大きな謎でしたが、トノーニは意識の単位として「Φ(ファイ)」を生み出し、脳と意識の関係性を明らかにしました。
脳と意識に関しての本の中では間違いなくトップクラスの良書であり、読み終えると文字どおり世界が変わって見える本でもあります。
脳と意識を理解したいのであれば、必ず読んでもらいたい1冊です。
✅意識の正体と進化に興味がある人
錯覚の科学/クリストファー・チャブリス
8冊目は、クリストファー・チャブリスの「錯覚の科学」です。
この本は、人間の注意・記憶・直感がいかに不確かで誤りやすいかを実験と実例をもとに解説しています。
特に有名な「ゴリラ実験」では、目の前の異常にすら気づけない選択的注意の限界を示し、私たちが思っているほど自分の認知能力は正確ではないことがわかるのがおもしろいです。
また、記憶は固定された記録ではなく変化しやすいものであり、直感や経験が必ずしも正しい判断を導くわけではないと解説しています。
日常の判断ミスの原因を科学的に捉え直す一冊です。
✅人間の思い込みや記憶の限界を知って驚きたい人
奇跡の脳/ジル・ボルト テイラー
9冊目は、ジル・ボルト テイラー「奇跡の脳」です。
この本は、脳科学者である著者自身が脳卒中を体験し、左脳の機能を失ったことで得た、右脳的世界の感覚と回復の記録を描いた実話となっています。
左脳の言語や論理が失われたことで、著者は時間や境界のない平和で一体感のある意識状態を書き綴っていて、興味深くてかなりおもしろいです。
科学とスピリチュアルの視点を融合させながら、脳の働きと意識の本質、人間の可能性を問いかける一冊。
✅脳卒中からの回復を通じて脳の働きを体感したい人
たった12週間で天才脳を養う方法/サンジェイ・グプタ
最後は、サンジェイ・グプタの「たった12週間で天才脳を養う方法」です。
著者は脳神経外科医であり、科学的根拠に基づいて「脳を若く、鋭く保つための習慣」を紹介する実用書となっています。
運動・睡眠・食事・学習・人間関係の5つの柱が脳の健康に不可欠であり、それぞれに具体的な改善方法を提示しているので、すぐに実践できるのがおすすめ。
認知症予防にも効果的で、日常に取り入れやすい脳活習慣をおしえてくれる本です。
✅日常生活で脳を若く保ちたい実践派の人
まとめ:脳科学を学べば見える世界が変わる
脳科学はとても興味深い分野です。
心理学は心の動きを扱うのに対し、脳科学では人間の頭の中に存在する脳という物体の機能を探求します。
脳はまだまだ謎に満ちていますが、それがまた知的好奇心を刺激する最高の学問です。
もし、少しでも人間や脳のはたらきに興味がある人は、ぜひ今回の記事で紹介した本を読んでみてください。
脳科学を学び、脳のはたらきを知る前と後では、見える世界がまるで変っているはずです。












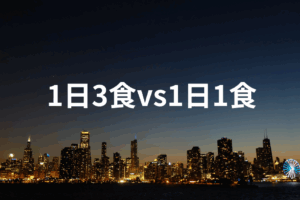



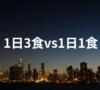
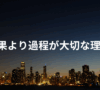
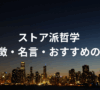
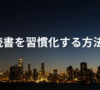
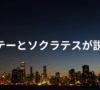
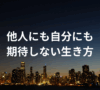
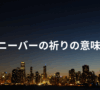


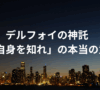
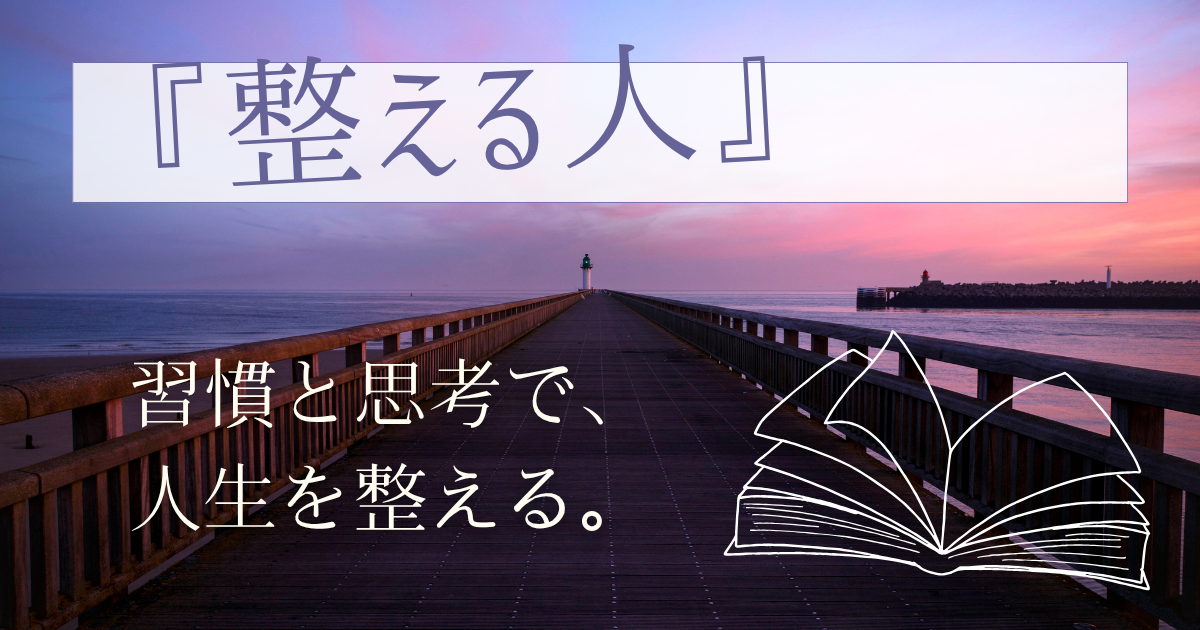
-300x158.jpg)


ありがとうございました。