最終更新日 2025年6月19日
古代ギリシャ・ローマ時代には、さまざまな言葉が存在します。
言葉にはたくさんの意味が込められていて、文脈によっても意味が変わるものが多いです。
たとえば、アリストテレスが提唱した「エウダイモニア」という言葉には、「幸福」という意味だけでなく、「繁栄」や「安寧」といった意味もあります。

この記事で取り上げるのは、ソクラテスがより良い人生に不可欠なものだと述べた「アレテー(徳)」という言葉について。
アレテーには「徳」という意味以外にも、人間の美点、すなわち絶対的価値の源という意味があり、ソクラテスからプラトン、アリストテレスからストア派まで受け継がれてきた言葉です。
ソクラテスが述べたアレテーとはどういうものなのか、アレテーの意味について深く知りたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
アレテー(徳)とソクラテス
アレテー(徳)とは、「卓越性」と訳され、簡単に言えば「人間が持つ道徳的な卓越さ」のことです。
アレテーがもっとも重要視されたのは古代ギリシャ・ローマ時代のことで、この時代は善や徳に沿った生き方がもっとも優れていると言われていました。
ソクラテスは「ただ生きるのではなく、より良く生きなければならない」と述べましたが、ソクラテスはより良く生きるためにアレテーが不可欠だと思っていたのです。

というのも、人生で後悔したり生きづらさを感じるのは、その多くはアレテーが欠けた生き方をしていることが多いからです。
ムソニウス・ルフスいわく、「人間は生まれつき美徳に惹かれる生き物である」。
つまり、アレテーに沿った生き方は人間の本能的な生き方なのです。
ソクラテスが唱えたアレテーの意味
古代ギリシャの哲学者であるソクラテスは、「知恵・勇気・自制・公正」の四元徳を何よりも重視していました。
四元徳については、以下の記事で詳しく解説しているので、興味がある人は読んでみてください。
言うまでもなく、四元徳とはアレテーのことです。
「人間の価値は、どんなときにも活用できる知恵と、倫理的・道徳的に沿った生き方をする勇気と、欲望に溺れないよう常に自制心を保ちつつ、誰にでも対等・平等に接する公正さを持つことにある」と、ソクラテスは述べています。
令和の時代に生きる私たちは、古代ギリシャに生きているわけではありませんが、四元徳についての考え方は現代社会に生きる人たちにも役立つものです。
昔よりも豊かになり、仕事をして自分でお金を稼げるようにもなり、行きたい場所や食べたいもの、やりたいこともある程度なんでもできる時代に生きていながら、孤独感や疎外感を感じている人、生きづらさや不幸を感じている人がたくさんいます。
大事なのは、知恵と知識を身につけ、自分の意志に従う勇気を持ちつつ、自制心を持ちながら他人に対して広い心を持って接すること。
ソクラテスやプラトン、アリストテレスといった古代ギリシャの哲学者たちが重んじていたアレテーは、決して誰にも奪われることがない、自分の価値と人間性を高めてくれるものなのです。
ストア派の四元徳とアレテー
ソクラテスの意思を引き継いだ哲学である「ストア派」の人たちも、人生をより良く生きるためには「知恵・勇気・自制・公正」の四元徳が必要だと考えていました。
ストア派とは、四元徳に沿った生き方をすることで、「アパテイア(不動心)」に達することを目的する哲学派のことです。
ストア派とアパテイアについて詳しく知りたい人は、以下の記事を読んでみてください。
ストア派の言う「知恵」とは、複雑な状況や環境の中で生き抜く知識のこと。
「勇気」とは、すべての事柄に対し、物理的かつ倫理的に正しいことをする勇気のこと。
「公平」とは、すべての人に対し、地位に関わらず公平かつ親切に接すること。
そして「節制」とは、人生のあらゆる面において、節度を持って自制すること。
とはいえ、人間にはアレテーに沿った生き方や、何事にも動じないアパテイアの心を持つことはほぼ不可能です。
ストア派の哲学者であるセネカも、アレテーを備えた人間を「賢者」と呼び、賢者についてこう述べています。
「賢者はそう簡単に見つかるものではない。賢者はまれな存在であり、長い年月を経てようやく現れる。」
その一方で、アレテーや四元徳を指針として人生を生きることについては、こう述べています。
「賢者になることは難しいが、賢者を目指すことは誰にでもできる。それが幸福への道だ。」
アレテーも四元徳も、「より良く生きよう」とする人たちの指針となるものなのです。
アリストテレスの最高善とアレテー
アリストテレスは、ソクラテスのアレテーを別の形として捉えました。
ソクラテスがアレテーに沿った生き方を提唱し、その弟子であるプラトンはイデア論を背景とした善のイデアを提唱し、ストア派は四元徳を重視しました。
これらは言い方こそ違うものの、すべてソクラテスのアレテーが基点となっています。
そして、アリストテレスもアレテーを別の言い方で表現しました。それが「最高善」というものです。
アリストテレスは最高善を人間の究極目的と考え、エウダイモニア(幸福)になるために必要なものだと捉えていました。
アリストテレスにとってのアレテーとは幸福そのものであり、最高善に至るためには観照的な活動が必要だと述べ、それこそアレテーに沿った魂の活動であると説いた。
しかし、アリストテレスも人間は最高善にたどり着けるとは思っていませんでした。
観照的生活は神的な生活であり、人間には属さないものだと思っていたからです。
アリストテレスはソクラテスのアレテーを否定したとも言われていますが、古代の哲学が目指すところはどれもほとんど変わりません。
それは、人間の幸福であり、より良い人生というものです。
ソクラテスの「より良い人生」とアレテーの関係性
古代ギリシャでは「人間性」こそ本当に価値のあるものであり、その人間性を磨くためにアレテーという徳に沿った生き方をするのが大切だと思われていました。
しかし、現代ではアレテーに沿った生き方をするのは難しく、「徳」と聞いただけで反射的に敬遠する人も多く、道徳と聞けば堅苦しいものだと思う人も少なくありません。

ですが、私たちは賢者になれないとしても、アレテーに沿った生き方を実践し、心豊かに幸福に生きることはできます。
もう一度セネカの言葉を引用します。
「賢者になることは難しいが、賢者を目指すことは誰にでもできる。それが幸福への道だ。」
アレテーに沿った生き方を実践することで、人は幸せに生きることができるのです。
アレテーは生き方の指針となる言葉
自分はストア派の思想に感銘を受け、ストア派の生き方に大きな影響を受けてきました。
今でも、迷ったときや悩んだとき、選択や決断に迷ったときなどはストア派の考えに従って意思決定をおこなうことが多いです。
でもそれは、ストア派として生きているわけではなく、日々の生活の中でストア派の考えを取り込める場面において参考にしているのです。

ソクラテスやプラトン、アリストテレスやストア派といった哲学の多くは理想主義であり、人間の生き方は「こうあるべきだ」と説く学問です。
ですが、私は人間に「こうあるべき」という生き方は存在しないと思っています。
そして、「~であるべき」と言うのは、その人の理想と願望が入り混じっている状態です。
アレテーにしても、徳に沿った生き方をするのは大切ですが、アレテーを実践しながら生きられる人は現実にはほとんどいません。
ですが、そうだとしても、「より良く生きる」という目的のために、アレテーに沿った生き方を指針とすることには意味があると思っています。
アレテーには倫理が不可欠
アレテーは「人間が持つ道徳的な卓越さ」のことを指しますが、それは「道徳的に優れていればいい」というわけではありません。
より良い人生には、道徳と合わせて倫理も必要なのです。
ストア派の哲学は「論理学」「自然学」「倫理学」の3つで構成されていますが、その中でも倫理学はストア派がもっとも重要視した学問でもあります。
道徳性だけが卓越していても、倫理が歪んでいてはより良い人生は生きられません。
倫理とは、「何が正しくて、何が間違っているか」を判断するときの根拠のこと。
一般的には、道徳と倫理は一緒のものと考えられていますが、ストア派の倫理学は「より良い生き方」を説く学問であり、言葉の意味からしてまったくの別物です。
倫理と道徳はコインの表と裏の関係性であり、「倫理なくして道徳なし、道徳なくして倫理なし」とも言えます。
言うまでもなく、アレテーは道徳と倫理が合わさった姿で、人間の生き方としては最高のものです。
しかし、最高であるがゆえに賢者でしかたどり着けません。

「何が正しいか」はわからなくても、「何が間違っているか」は比較的わかりやすいです。
人によって何が幸福かは異なりますが、不幸の原因は誰も似たようなもの。
倫理的な思考とはそういうものです。
つまり、正しいことがわからなくても、間違っていることを排除した結果、自然と正しい生き方ができるということ。
それが倫理的な生き方の指針です。
美徳こそもっとも価値あるもの
私は人生をより良く生きたいと思っています。
人生で少しでも楽しい時間を増やし、後悔する選択を減らし、できる限り充実した人生を送りたいです。
アレテーという言葉は、より良く生きるために大切な意味が込められています。
考えるべきは人間の理想の姿ではなく、どうすればより良く生きられるか。
アレテーは元々ソクラテスが提唱した概念です。
その後、プラトンが善のイデアを提唱し、プラトンの弟子であるアリストテレスが最高善とエウダイモニアという考えを唱えました。
ストア派も元々はソクラテスの哲学を主流としていたため、ストア派が唱える徳はアレテーを4つに分類した四元徳となったのです。
どの哲学者が唱えるアレテー(徳)も目指すところは同じ、「人生をより良く生きる」ためのもの。
アレテーがたとえ理想的なものだとしても、アレテーに沿った生き方を意識することで、日々の生活を充実したものにできます。
アレテーという言葉が教えてくれるのは、より良く生きるためには徳が必要ということであり、美徳こそ人間性の中でもっとも尊く、もっとも価値のあるものだということです。
【オススメです】電子書籍「自分を知る15の質問」が今だけ無料で貰えます

自分のやりたいことや自分軸の見つけ方がわかります。
「DISCOVERYメソッド」で学ぶことで、自分のやりたいことや自分軸の正しい見つけ方がわかり、もう他人に振り回されることがなくなり、自分がすべきことを自分で決断できるようになるでしょう。
まとめ:アレテーは幸せになるために役立つ言葉
今回の記事では、アレテーとは何かについて解説してきました。
まとめは以下のとおりです。
- アレテーとは人間が持つ道徳的な卓越さのこと。
- アレテーを唱えたのはソクラテスが起源。
- ストア派によってのアレテーは「知恵・勇気・自制・公正」の四元徳のこと。
- アリストテレスにとってのアレテーは「最高善」だった。
- アレテーのような生き方は理想であり、完璧には実践できない。
- アレテーはより良く生きるための指針となる言葉。
アレテーという言葉は人間の道徳的な卓越さのことであり、ストア派的に言うと「美徳に沿った生き方」という意味になります。
ストア派の美徳は四元徳で表され、それは「知恵・勇気・自制・公正」の4つです。
これらは人生をより良く生きる指針となるものであり、古代ギリシャでは幸せな人生を送るために不可欠なものだと言われていました。
そしてそれは現代でも変わりません。
アレテーや四元徳に沿った生き方をするのは、心豊かに、幸せに生きるために役立ちます。
一時的な喜びではなく、もっと深い喜び、本当の幸せを感じるために、アレテーに沿った生き方をしてみるのも、いいかもしれません。




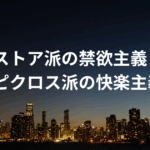







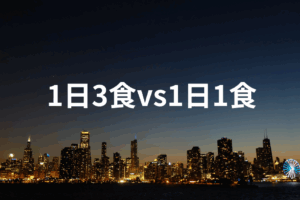



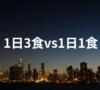
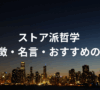
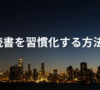
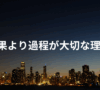
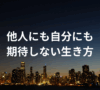

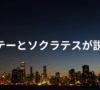

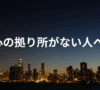
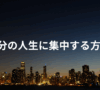
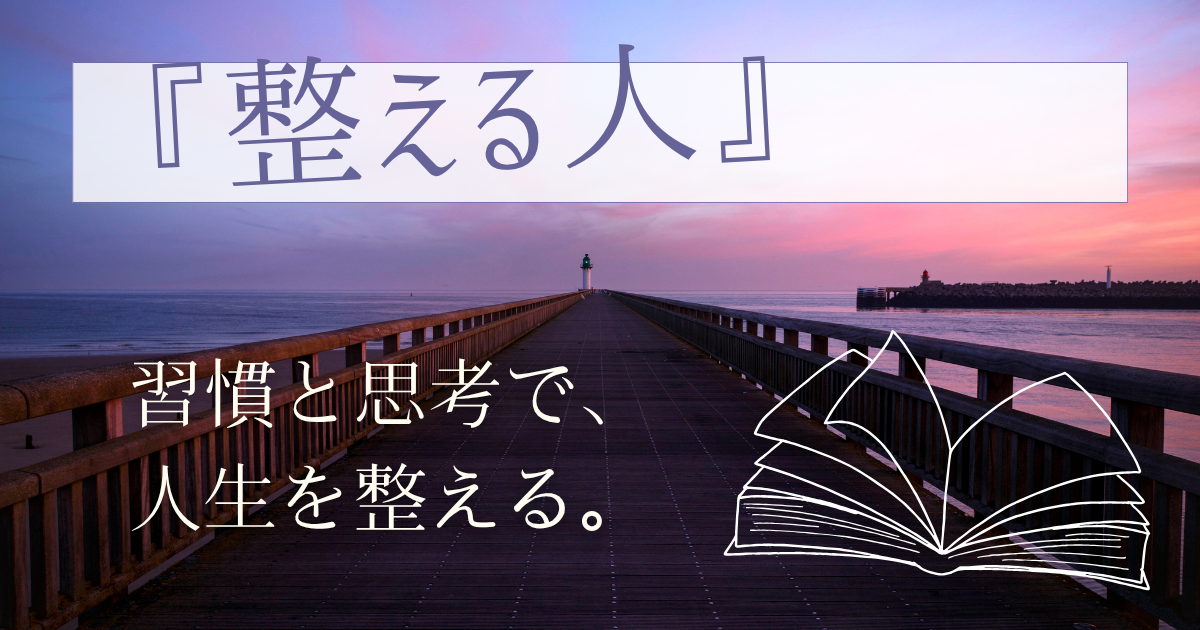
-300x158.jpg)

