最終更新日 2025年6月20日
古代ギリシャの哲学であるストア派の哲学には、「アパテイア」という言葉があります。
これは「不動心」とも言われるもので、怒りや不安といった感情に振り回されない状態のことです。
ストア派では、心の状態としてアパテイアを目指すことが、より良い人生、幸せに生きるために必要なことだと思われていました。
この記事では、ストア派のアパテイアについて詳しく解説していきます。
アパテイアとはどういうものなのか知りたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
ストア派のアパテイアとは
アパテイアとは、古代ギリシャの哲学である、ストア派が好んで使っていた言葉です。
近年ストア派の哲学は世界中で注目されており、芸能人や著名人の間でも人生を生きる指針として役立つものとなっています。
ストア派の思想は、簡単に言うと「感情と欲求をコントロールし、より良く人生を生きる」こと。
そして、ストア派が感情と欲求をコントロールするために掲げた概念が、「アパテイア(不動心)」というものです。
アパテイア=心の平穏
ストア派のアパテイアとは、欲求や欲望、一時の感情などによって振り回されない精神的な状態のことです。
つまり、怒りや不安、恐怖や欲望に惑わされない心の強さを持っている状態になります。
こう聞くと、「そんなことは不可能だ」と思うかもしれません。

嫌なことをされればイライラしたり、不安の感情をすべて失くすことは誰にもできません。
ストア派が否定しているのは、一時の感情に振り回されてしまうこと。
アパテイアとは、自分の感情をしっかりコントロールすることで、心の平穏を実現しようとする思想なのです。
外的な出来事に振り回されない状態
人生では毎日さまざまな出来事に直面します。
仕事や学校での人間関係にはじまり、毎日思い通りにいかないことがたくさん起き、腹立たしいことからイライラすることまでたくさんあるのが人生です。
ですが、自分の身に降りかかる出来事の大半は、自分ではどうすることもできません。
ストア派のアパテイアは、外的な出来事、自分でコントロールできない出来事に振り回されるなと戒めています。
好きな人に好きになってもらいたくても、他人の心は自分では変えられない。
仕事の残業にイライラしたとしても、一日の仕事量は自分の意思で変えられない。
車の渋滞や電車の遅延も、たとえどれだけ急いでいて、どれだけ周りに怒鳴り散らかそうが解消されるわけではない。
こうした「自分の力でコントロールできないもの」を、コントロールしようと思ったとき、心の平穏が乱れることになります。
アパテイアの本質は、自分でコントロールできるものに集中し、自分ではコントロールできないものを放っておくことで、心の平静を達成することです。
自分の思い通りにならないことは放っておく
ストア派のアパテイアは、自分でコントロールできないものは成り行きに任せ、コントロールできないものに対する自分の心のコントロールに力を注ぎます。
つまり、自分の感情の手綱を握るということ。
ストア派の人たちは、自分の死や財産の没収という出来事に対しても、取り乱すことなく平常心を保っていました。

現代では普通に生きていれば命の危険や財産の没収はありませんが、外的な出来事に振り回されない心構えを持つことは、より良い人生を生きるためにも重要です。
思い通りにならないことを、思い通りにしようとすると、それが叶わなかったときにストレスを感じます。
ストア派では、「より良い人生=心の平穏」だったため、心の平穏を乱すのを避けることが、より良い人生だと考えられていたのです。
心の平穏を保つコツは、自分の意思でどうにかなるものだけに集中し、自分の意思ではどうにもならないことは放っておくこと。
アパテイアは、ストレス社会と言われる現代においても、有用な言葉と言えます。
アパテイアは感情がない状態ではない
アパテイアのためには、自分でコントロールできるものと、できないものを見極めることが大事です。
自分でコントロールできないものに対する考え方や捉え方は、自分次第でコントロールすることができます。
さきほども言ったように、仕事が忙しいからと文句や愚痴を言ったところで仕事量が減るわけではありません。
行きたいお店が込んでて入れないからといって、イライラしても何も変わりません。

それよりも、自分には関係のないことは放っておくことで感情をコントロールし、心を平穏に保つことのほうが幸せに生きられます。
よく、アパテイアは「不動心」という言葉が独り歩きし、「感情がない状態」と誤解されますが、それは間違いです。
アパテイアは感情がない状態ではなく、感情をコントロールしている状態。
つまり、自分でコントロールできないものを放っておくことで、自分の感情をコントロールするのが、ストア派のアパテイアというもの。
ストア派は感情がない人たちではなく、感情と欲求をコントロールし、心の平穏から幸せな人生を目指す人たちです。
アパテイアとほかの思想とのつながり
ストア派のアパテイアは、より良い人生、幸福な人生に役立つものです。
ですが、実はアパテイアの本質である「自分でコントロールできるものとコントロールできないもの」という考え方は、ストア派以外の哲学や思想にも見られます。
とくに関連性が高いのは、エピクロス派の「アタラクシア」、ラインホールド・ニーバーの「ニーバーの祈り」、そしてアドラー心理学の「課題の分離」です。
アパテイアとアタラクシアの違い
ストア派のアパテイアという思想は、よくエピクロス派の「アタラクシア」という考え方と比較されます。
ストア派のアパテイアは、自分にコントロールできないことは成り行きに任せ、自分にコントロールできるものにだけ力を注ぐ思想です。
一方、エピクロス派のアタラクシアは、できる限り世間から遠ざかった隠遁生活を送り、自分にとって本当に大切な人たちと友情や愛情を育み、心と人生の充実を実現するという思想になります。
✅ストア派:自分にコントロールできないことは成り行きに任せ、自分にコントロールできるものにだけ力を注ぎ、心の平穏を実現する。
✅エピクロス派:世間から遠ざかり、自分にとって大切な人たちとだけ関係を育み、心の平穏を実現する。
一見、両者の考えは異なるように見えますが、ストア派のアパテイアもエピクロス派のアタラクシアも、根本的な考え方は共通しています。
どちらの哲学も「心の平穏」「人生の充実」を目的としているのです。

ストア派のアパテイアもエピクロス派のアタラクシアも目指す場所はひとつ、心の平穏です。
ストア派とエピクロス派の違いについては、以下の記事で解説しているので、興味がある人は読んでみてください。
出来事ではなく、出来事に対する反応が大事
ストア派の哲学者であるエピクテトスは、「人を不安にするのは出来事そのものではなく、出来事についての私たちの判断だ」という言葉を残しています。
つまり、怒りや悲しみ、苦しみや絶望を感じるのは出来事そのものからではなく、出来事に対する自分の考え方で不幸になっているということ。

外出していて雨が降ってきたときに、「なんで降ってくるんだ」とイライラするのか、それとも「雨が降ってきた、傘を差そう」と思うのか。
どちらも同じ出来事、「雨が降った」という出来事が起きていますが、それに対する反応によって心の状態はまったく違ったものになります。
どちらのほうがアパテイアに近いかは、言うまでもありません。
エピクテトスはストア派のアパテイアを実践し、「自分でコントロールできるものとできないものを、しっかりと区別せよ」と述べています。
また、ラインホールド・ニーバーが書いたとされる「ニーバーの祈り」にも、上記のエピクテトスの言葉と同じようなことが書かれています。
神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。
変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。
ニーバーの祈りの意味については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも興味がある人は読んでみてください。
さらに、アパテイアの考え方は、現代ではアドラー心理学の「課題の分離」という考え方でも知られています。
アパテイアとアドラー心理学の「課題の分離」
アドラー心理学は、フロイトとユングに並ぶ3大心理学者の1人、アルフレッド・アドラーの心理学です。
近年では「嫌われる勇気」という本で一般的にも広く知られるようになり、現代ではフロイトやユングよりもアドラーの思想が注目を浴びています。
そしてアドラー心理学の核となっている考え方の1つに「課題の分離」があり、この考え方についてアドラーは以下のように述べています。
まずは「これは誰の課題なのか?」を考えましょう。そして課題の分離をしましょう。
どこまでが自分の課題で、どこからが他者の課題なのか、冷静に線引きするのです。
そして他者の課題には介入せず、自分の課題には誰ひとりとして介入させない。
これは具体的で、なおかつ対人関係の悩みを一変させる可能性を秘めた、アドラー心理学ならではの画期的な視点になります。
これはストア派のアパテイアである、「コントロールできるものとコントロールできないものを区別せよ」と同じ意味です。
「他人の心は自分にはどうしようもできない、だからそんなことは気にする必要はなく、自分は自分のことだけに集中せよ」という意味。
アドラー心理学は、主に対人関係に重きを置いている心理学ですが、ストア派のアパテイアも、アドラー心理学も根本的には同じ考え方です。
すなわち、「自分の力が及ぶもの以外は放っておこう」。
【オススメです】電子書籍「自分を知る15の質問」が今だけ無料で貰えます

自分のやりたいことや自分軸の見つけ方がわかります。
「DISCOVERYメソッド」で学ぶことで、自分のやりたいことや自分軸の正しい見つけ方がわかり、もう他人に振り回されることがなくなり、自分がすべきことを自分で決断できるようになるでしょう。
【まとめ】アパテイアは現代でも役立つ実践的な知恵
ストア派の思想は約2000年前のものですが、アパテイアのように現代社会でも役に立つものがたくさんあります。
ストア派の実践者であるセネカは、アパテイアを実践的な生活の指針と捉え、日常生活での感情の管理や徳の実践に重点を置きました。
現代に生きる私たちにとっても、アパテイアは生きるのに役立つ実践な知恵であり、より良い人生に不可欠なものです。
アパテイアを完璧に実践することは難しいかもしれませんが、自分のできる範囲でコントロールできるものと、できないものを区別してみましょう。





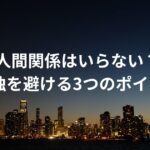
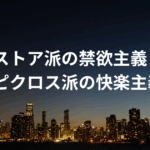


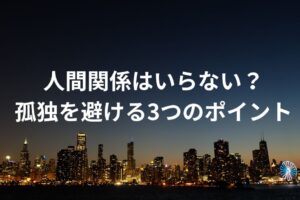

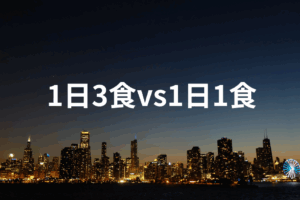



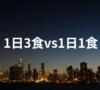
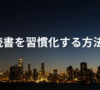
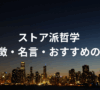
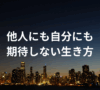


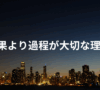
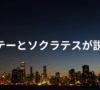
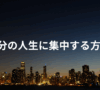
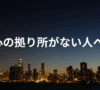
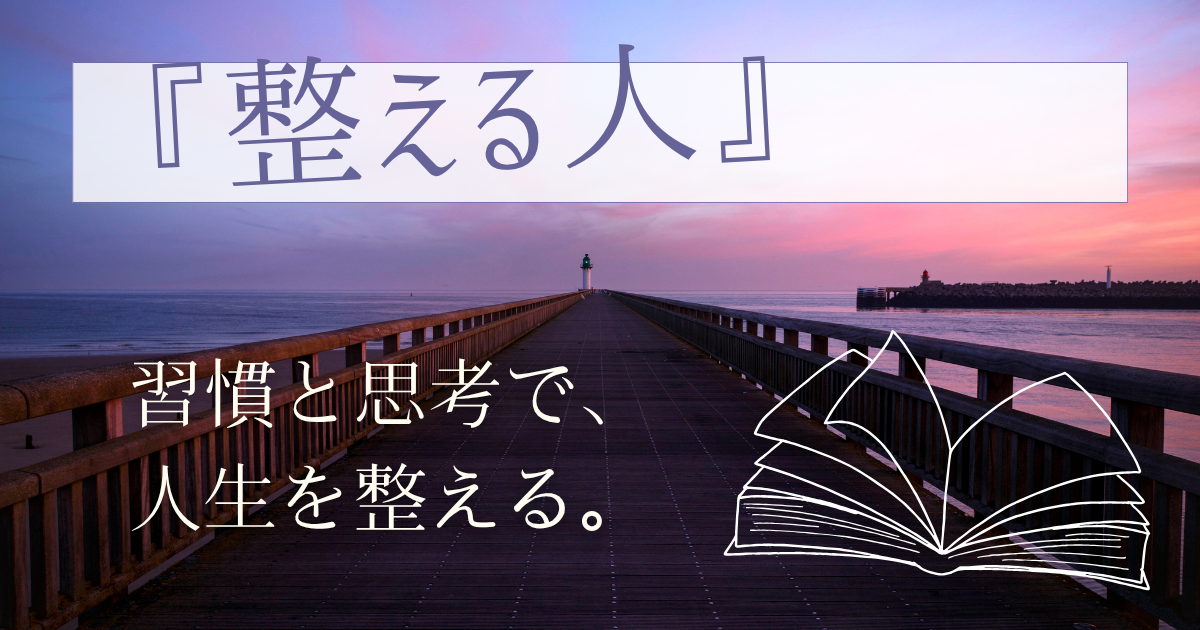
-300x158.jpg)

