最終更新日 2025年6月12日
こんにちは、竜崎(@ddd__web)です。
みなさんは「温厚な人」と聞くと、どんな人を思い浮かべるでしょうか。
一般的には温厚な人というと、怒らない人や心が広い人、器が大きい人や優しい人などが挙げられます。
自分も昔は、温厚な人は優しくて心が広い人だと漠然と思い込んでいました。
でも、本当にそうなのか。
- 人は優しければそれでいいのだろうか?
- 心が広いことは、本当に人間として優れていることなのだろうか?
- どんなに嫌なことがあっても怒らない人は、本当に温厚な人だといえるのだろうか?
現代では言葉の意味を自分たちの都合のいいように解釈する人がたくさんいます。
「自立」という言葉にしても、世間では「1人暮らし=自立」だと言われていますが、人間としての本当の自立は一人暮らしではありません。
自立については、以下の記事の中で詳しく解説しているので、興味がある人は読んでみてください。
そして、「温厚な人」というのも自立と同じく、現代人の都合に合わせて「優しくて心が広い人」だと解釈されています。
結論から言うと、温厚な人とは優しい人のことではなく、「しかるべき人に対して、しかるべき方法で、しかるべき時に、適切に怒る人」のことです。
そこで今回の記事では、温厚な人とはどんな人のことなのかについて詳しく解説していきます。
温厚な人は決して怒らない人でも、優しい人でも、器が大きい人でもありません。
温厚な人について深く考えてみたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
世間が思う温厚な人とは
社会の中ではなぜか「怒らない人」が尊敬されます。
嫌なことをされても笑顔を保ち、挑発されたりバカにされたりしても笑い飛ばし、怒りに振り回されず感情をコントロールできる人。
そうした人が、世間一般には人間的に優れていると思われています。
ですが、世間一般で評価される人が優れている人とは限りません。
怒らないだけで他人から好かれ、他人から好かれることが優れた人間性とは限らないのです。
優しい人が好かれる世界
友達や恋人、仕事の同僚などの人間関係がある以上、むやみやたらと感情に振り回されないことは大事です。
感情に振り回されると冷静に物事を考えられなくなり、自己中心的な言動を取りがちになる。
恋愛において感情が致命的となるのは、自分目線でしか物事を考えられなくなってしまうからです。
恋人のことで頭がいっぱいになってしまっている、「恋愛依存症」などはまさにその典型例だと言えます。
職場や友達関係の中にも、感情的で怒りっぽい人が何人かは見当たりますよね。
怒るほどのことでもないのにすぐ不機嫌になったり、いつも感情的で冷静に話ができなかったりなど、そうした人と付き合うのは疲れると思っている人も少なくありません。
だからこそ、「優しい人」や「心が広い人」がみんなから好かれやすくなっているのです。
優しい人が好かれるのは、感情的な人間と付き合うのが疲れるから。
優しくて心が広い人は感情的な行動も少ない。理性を使って冷静に物事を考えることができる。
そして、一般的にはそうした人こそ「温厚な人」と思われています。
温厚な人=自分の利益になる人
でも、優しい人や心が広い人は、本当に温厚な人だと言えるのでしょうか。
近年は、車のあおり運転やら無差別殺人など事件やトラブルが絶えない世の中ですが、なんだかんだいって優しい人や心が広い人のほうが多いです。
特に日本人は道を聞けば親切に教えてくれるなど、他人に優しい国として他の国からも人気があります。
みんな自分に良くしてくれる人と付き合い、自分が気持ちよく関係を築ける人と仲良くし、自分と気の合う人を友達と呼ぶ。
温厚な人はまさに、友達や恋人にぴったりの人間だと思うでしょう。
ですが、肝心なことを忘れてはいけません。
人間関係の根底には少なからず「自分の利益」が存在しているのです。
温厚な人が社会的に評価されるのは「怒らないから」「優しいから」「心が広いから」。
しかしそれは、自分の利益に叶う相手だからそう評価しているに過ぎません。
つまり、
「自分の利益になる人⇒温厚な人」
という解釈になっているのです。
だからこそ、人は温厚な人が好きなのです。
温厚な人とは適切に怒りを用いる人
あくまで私の考えですが、本当の温厚な人とは何をされても怒らない人のことではありません。
誰にでも優しく、気遣いができ、心が広く、常に笑顔を絶やさない人のことでもありません。
人生哲学の祖とも呼べるアリストテレス風に言うと、温厚な人とは「しかるべき人に対して、しかるべき方法で、しかるべき時に、適切に怒る人」です。
しかるべき人に対して、しかるべき方法で、しかるべき時に、適切に怒る人 。
温厚な人は他人のことを考えて怒る
温厚な人は怒るべきタイミングを間違えず、本当に必要なときに「怒り」の感情を適切に使います。
感情に振り回されるのは恋愛や友人関係において致命的となりますが、しかるべきときに怒りの感情を使うのは間違いではありません。
たとえば、友達が何か間違ったことをして周りに迷惑をかけたり、犯罪に手を染めたとすれば、しっかりと怒りの感情を使って適切に怒る。
「どんなことでも受け止める」というのは聞こえはいいですが、それは優しさではなくただの甘えです。
社会的に評価される優しい人は、何があっても笑顔で受け止め、許してくれます。
ですが、長期的に見るとそれは本人のためにはなりません。
温厚な人はただ優しさを差し出すのではなく、相手の先のことまで考えた上で、怒りの感情を本人のために使う。
それができる人こそ、本当に温厚な人なのです。
過度な優しさは人をダメにする
優しい人や心が広い人のことを悪く言う人はいないでしょう。
優しい性格をしていれば他人からも好かれやすく、友達もたくさん増えます。
だから私たちは子どもの頃から、「人には優しくしなさい」と親や学校の先生から教えられるのです。
ですが、優しさは時として人をダメにしてしまいます。
よく言われるように「甘やかしてばかりいると人はダメになる」のです。
他人から優しくされすぎたり、何をしても許してもらってばかりいると、どんどん調子に乗って自分に都合のいい人間関係しか求めなくなります。
そして、他人が常に優しい態度で接してくれるのが自分の中の人間関係のデフォルトになり、ちょっとでも自分に気に食わないことがあると、「そんな些細なことで怒るなんて気が小さい」と思うようになります。
これは「優しい」という言葉を自分に都合よく解釈している人にありがちなことです。
優しさに囲まれている環境では、自分がいかに恵まれているのかがわからなくなってしまう。
それが人を傲慢にし、精神的にも成長しない人間になるのです。
優しい人は他人の思い通りになる人のこと
「些細なことで怒るなんて気が小さい」という言葉は、自分の思い通りにならなかった言い訳として使われていることが多いです。
もちろん、中には本当に些細なことで怒鳴り散らす人もいます。
コンビニにお気に入りのパンが売ってないだけで不機嫌になる人もいますし、電車に乗り遅れてイライラしたり、ちょっと肩がぶつかっただけでイチャモンをつけてくる人もいます。
ですが、多くの人は「優しさ」を自分に都合よく解釈し、自分の思い通りのことをしてくれない人は「優しくない」「冷たい」「性格が悪い」とレッテルを張り付ける。
つまり、世間的に優しい人になるためには、他人の思い通りになる必要があるのです。
他人が期待している行動をし、他人の嫌がることはせず、他人の思い通りに優しく接する。
これが世間的な優しい人です。
しかし、「温厚な人」と「優しい人」は違います。
優しい人は他人を甘やかし、人をダメにしてしまう可能性がありますが、温厚な人は怒りの感情を適切に使います。
何度も言いますが、他人のことを思い、本気で怒れる人こそ温厚な人なのです。
温厚な人は感情の使い方が上手い
温厚な人は適切に怒りを使うことができますが、それには感情のコントロールが欠かせません。
アドラー心理学では「怒り」などの感情はコントロールが可能だと言われていて、「嫌われる勇気」という本の中で、怒りという感情がコントロール可能である例を紹介しています。
例えに使われているのは、以下のような状況です。
子どもが悪いことをし、それに対して怒っている母親がいる。
母親は顔を真っ赤にして怒鳴り声をあげて子どもを叱っているが、そこに電話がかかってきた。
母親は電話に出たが、相手が子どもの学校の先生だとわかると、急によそ行きの高い声で丁寧な挨拶をして対応している。
怒りという感情がコントロール不可能だったなら、電話に出た瞬間に対応を変えることはできませんよね。
この例からわかるように、人は怒りを含めた感情のコントロールが可能で、感情に振り回されないように対処することもできます。
温厚な人とは、こうした感情のコントロールに長けた人間です。
温厚な人は万人には好かれない
何度も言いますが、多くの人は言葉の意味を自分の都合のいいように解釈しています。
「性格がいい」という言葉も、「自分にとって気持ちのいい相手かどうか」で性格の良さを定義しているのがほとんどです。
それはつまり、温厚な人でも万人にとっては温厚な人とは思われないということです。
温厚な人は万人に好かれない。
ですが、温厚な人が温厚な人だと思われないからといって、それは温厚な人に価値がないというわけではありません。
たとえ周りからどう思われていようが、温厚な人は人間的に優れている人格者です。
SNSのフォロワーでマウント取りしている人は多いですが、人間的な価値は数値化できません。
それと同じく、学歴や職歴、肩書きや地位といったものでも相手の人間性なんてほとんどわかりません。
犯罪者のいつも通りの日常を観察していても、その人が犯罪者かどうかはわからないのです。
人の本当の人間性が表に出るのは、追い詰められたときだけ。
温厚な人は優しい人のように世間的には評価されないかもしれませんが、わかる人はきちんとわかってくれるはずです。
温厚さとは人間性
人間と動物が違うのは、人間には自分の感情をコントロールできる理性がある点です。
欲求や欲望、嫉妬や怒りの感情に振り回されるのは動物と変わりありません。
ライオンには牙が、クマには爪があるように、理性は人間にのみ備わっている武器です。
人間は理性を使って感情をコントロールできる。
ですが、その武器も普段から磨いておかなければすぐに錆びついてしまいます。
温厚な人になるには、自分の感情をコントロールできなければなりません。
一時の感情に振り回されるのではなく、理性で感情をコントロールすること。
中年の大人が欲求や欲望、嫉妬や憎しみといった感情から悪質な事件を起こして捕まったりしているのは、感情のコントロールができないからです。
私たち人間は理性を使って動物から脱皮し、社会の中で生きる大人として感情を手懐けなければなりません。
温厚さとは、言い換えれば人間性です。
感情を手懐け、冷静に物事を判断し、自分にも他人にも適切な感情を用いることができる人。
温厚な人は優しさを履き違えず、感情を適切かつ巧みに利用する、人間性に優れた人なのです。
【まとめ】温厚な人と優しい人の違いを理解する
今回の記事では、温厚な人とはどんな人のことなのかについて詳しく解説してきました。
まとめは以下のとおりです。
- 世間が思う温厚な人は「自分の利益になる人」のこと。
- 本当に温厚な人は「適切に怒る人 」のこと。
- 温厚な人は怒りの感情を適切に使う。
- 優しくするだけでは人はダメになる。
- 温厚な人は万人には好かれない。
- 人間性に優れた人が、温厚な人。
世間が思う温厚な人と、本当に温厚な人には違いがあります。
もちろん、この記事で解説してきたことは私の考えでしかないので、意見が違う人もいるでしょう。
人は言葉の意味を自分の都合のいいように解釈しがちですが、それでは自己中心的な人間になってしまいます。
温厚な人に限らず、言葉の本当の意味を自分の頭でしっかり考えることが大事です。
優しい人や温厚な人の違いを理解すれば、人間的にも精神的にも成長でき、人間関係も今より充実したものになるでしょう。
【Twitter】
【note】
【お問い合わせ】












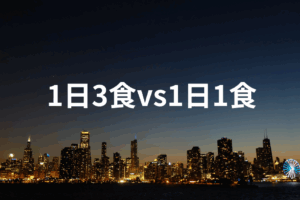



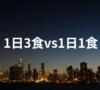
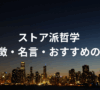
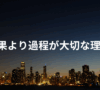
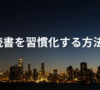
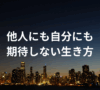


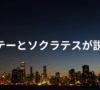
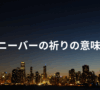
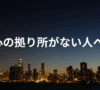

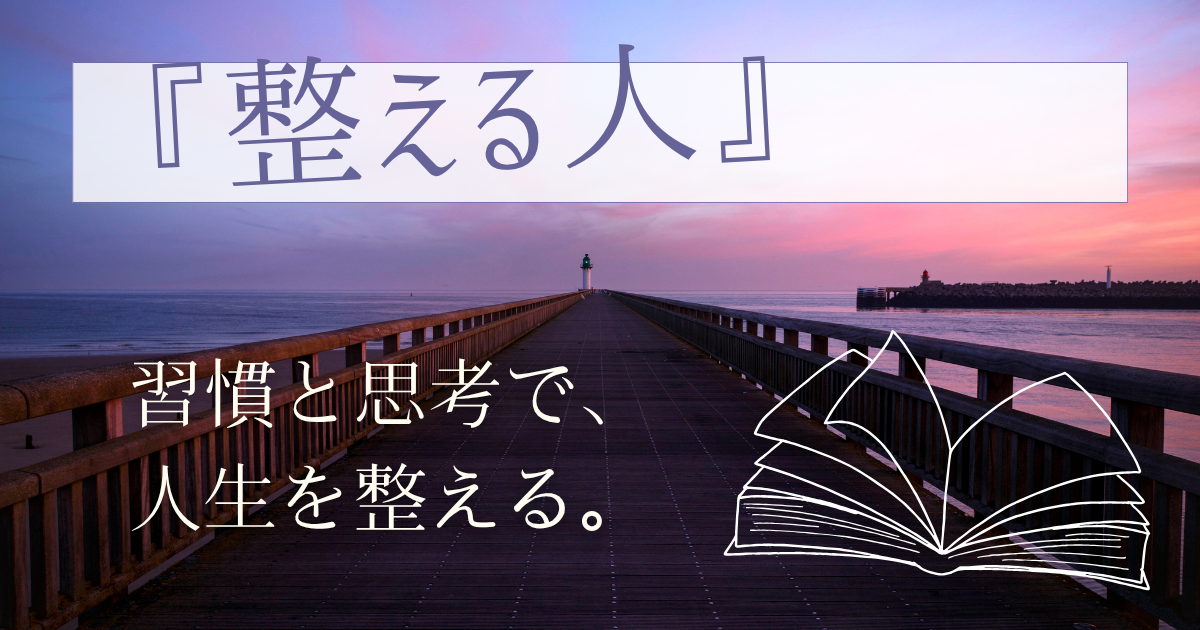
-300x158.jpg)


コメントを残す